お知らせ
本作の続編となる作品「津島 ―福島は語る・第二章―」の公開が決定しました(2024年3月2日より公開)。
詳細は以下リンクより、公式サイトをご確認ください。
「津島 ―福島は語る・第二章―」
新型コロナの影響で中止/延期になる上映会があります。お出かけの前に、必ず主催者のサイトなどでご確認ください。
<自主上映会募集>
小規模なグループや友人同士など仲間内での少人数の企画から本格的な上映会まで対応可能です(10人未満・上映料1万円から)。土井敏邦の講演依頼も募集しています。
 自主上映申し込み
自主上映申し込み
<お知らせ>
「文化庁映画賞 文化記録映画 優秀賞」 を受賞しました。
いまを生きるすべての人たちへ
分断された私たちが語り継ぐ14のメッセージ

作品紹介
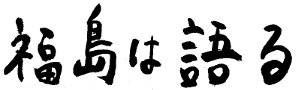
監督・撮影・編集・製作: 土井敏邦
2018年/日本/カラー
劇場版:170分(2時間50分)
完全版:320分(5時間20分)
題字: 高橋長英
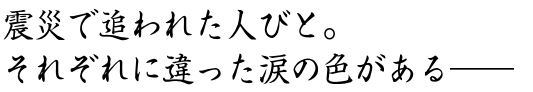

原発事故から8年が過ぎました。日本は、2020年の東京オリンピックに向けて浮き足立ち、福島のことは「終わったこと」と片づけようとしているように感じます。しかし、原発事故によって人生を変えられてしまった十数万人の被災者たちの心の傷は疼き続けています。
100人近い被災者たちから集めた証言を丹念にまとめました。その“福島の声”を、忘却しつつある日本社会に届けたいと願い、この映画を制作しました。
2018年 土井敏邦


コメント
佐藤忠男/保坂展人/吉原毅/金滿里/松元ヒロ/花田達朗
- 佐藤忠男 (映画評論家)
- 数々の作品で高い評価を受ける土井敏邦監督が、100 人を超える証言者の中から選び抜いた14 人の現在進行形の”福島の声”を、4 年かけて映像作品に仕上げた。日本に住むすべての人に向けて語り継ぐ、珠玉の証言ドキュメンタリー。原子力発電所の事故の被害者たちが、受けた心の傷を、その本人たちが、あくまでも静かに、そしてあくまでも深く掘り下げて語るのを、真剣に聞く映画です。人々の表情が、口調が、これほど雄弁に一つの深い思いに結集した映画が、これまでにあっただろうかと、私は驚き、感動しました。まれにみるドキュメンタリーです。
- 保坂展人(世田谷区長/ジャーナリスト)
- 東日本大震災の夜、私は一晩中、福島第一原発事故の深刻な事態を受け止めていた。そして、爆発と放射性物質の拡散。『福島は語る』は7年の歳月を経て、原発事故により避難を強いられた人たちの言葉を記録し、憤りと悔しさ、切なさと絶望、非情な事故によって奪われた人生を克明に語る映像作品だ。 この映画は涙なくして見ることは出来ないが、現在まで続く被害を封じ込めている「沈黙の圧力」とは、鈍感で浅薄な「無関心と忘却」だ。鉄の爪が大地に根ざして生きていた人々を容赦なく襲い、傷つけ、引き裂いた。この暴力に私たちひとりひとりが加担していないかを問いかけてくる。
- 吉原毅(城南信用金庫顧問)
- 映画『福島を語る』で、避難を強いられた人たちの生の言葉に触れると、大きな声で叫びたくなります。
«原発ゼロで日本経済を再生しよう»
原爆の被爆国でありながら原発事故をおこした日本が、何故危険な原発を推進するのか。それは、「原子力ムラ」という政官財がつるんだ巨大な利権集団が私利私欲の為に間違ったことを強引に続けているからです。7年の歳月が経ち、福島第一原発の悲劇の記憶が薄れる中、この映画では悲劇が終わるどころか拡散・膨張している現実を思い知らされます。 - 金滿里(劇団態変主宰)
- 福島の今を知りたいと思っていました。そこへ応える重要な映像に加え、自然が泣けるほど美しい。政府による無き者とあつかう、現代の棄民政策の実態が、ここにあると感じました。そこには、次には自分の番?から目をそらそうとする一般市民が透けて見え、福島は、収容施設で殺された園障碍者19名・現在生きている私たち障害者、と同じところにあると思います。怒り、は必要です!
- 松元ヒロ(コメディアン)
- 家を失い、家族を友を日常生活を失なった人々。「でもこの故郷、福島が好き。ここが故郷で良かった」と笑顔で言いながら泣いている人が私を更に泣かす。福島の四季、美しい景色をバックに流れるエンディング曲「ああ福島」でまた涙が…。あきらめずに生きている人たちがいる。
- 花田達朗(フリーランス社会科学者)
-
以下の文章は、花田達朗氏が個人サイト「サキノハカ」に2月5日に掲載された文章(ドキュメンタリー映画『福島は語る』を観た)ですが、著者の了解を得て、ここに転載します。
昨日、2月4日、土井敏邦監督のドキュメンタリー映画『福島は語る』を試写会で観た。14人の「被災者」のインタービューである。「フクシマ」についてのドキュメンタリーはこれまで何本も観てきたが、これは次元を超えている。月並みな言葉ではあるが、「最高傑作」だと思った。どうして私をしてそのように言わしめるのか。
理不尽さに対する悔しさ、怒り、無念さ、悲しみ。それらが深いところから、つまりこれまでじっと耐えて沈黙してきた深度から、肉声と表情で表出され表現されている。そのことによって、悔しさ、怒り、無念さ、悲しみがその深さと重さにおいて私たちに伝達可能になっている。私たちの方からすれば、つかもうとする意志さえあれば手が届くという形になっている。私がこれまでの様々な表現物にもどかしさを感じてきたのは、その深度に届いていないのではないかと感じさせられたからだ。この土井さんの作品によって、私たちはやっとその深度に届く手段を得ることができたと言える。この映画を観たあと、それから先のことは、それぞれの個人の領域の問題だ。私たち一人一人が考え、感じるための手段が与えられたということだけは確かなことだ。
「被災者」とは原発事故の犠牲者である。「犠牲者」と定義しなければならない。この世界、この社会は犠牲者を生み出しながら進んでいく。そこにおいて、犠牲者とは多くの場合、沈黙を強いられて、沈黙に行き着く。自分のことを「わかってほしい」と他者に語ることを試みたとしても、多くの場合、他者に拒絶されるからだ。犠牲者は少数者へと追い込まれ、それ以外の多数者はその少数者を記憶と視野から消し去っていく。記念日ごとに思い出しているかのように演出してみたところで、それは自分たちの不作為を正当化するための偽装でしかない。
ある日突然放射能によって日常と生業、自然と故郷を奪われた理不尽さ、そして犠牲者としてその理不尽さを語ることを奪われた理不尽さ、犠牲者はこの二重の理不尽さのなかを生きている。その接合した二重性が固い沈黙を生み出す。そのことを、ここに登場する福島の14人の人々は体験し経験してきたということがわかる。
土井監督は、そこにできあがった深く固い沈黙を切り開き、その人々から発話と表情を獲得して、私たちに映画という形で手の届くものにしてくれた。そのことによって、このドキュメンタリーに登場した人々、さらには同じような経験をした多くの「犠牲者」たちは、その思いが言葉と表情で語られ、他者に届けられる可能性を得たことによって、その思いのある部分だけだとしても救済されたと感じるのではないだろうか。どのような形、どのような手法によってであれ、権力の「犠牲者」を救うこと、それこそがジャーナリトの役割なのだ。
なぜこの14人の人々は沈黙を破って、語り始めたのだろうか。しかも深く豊かな言葉によって……。それは映画のなかでも聞こえてくるように、土井さんの問いかけがあったからであり、その横にカメラが据えられていたからである。証言した人々は土井さんに向かって、土井さんの目を見て、語っている。土井さんだからこそ語っているのである。そして、それが映像に記録されていることを意識し、受け入れたからである。公開され、他者に見せられることを受け入れて、語っている。カメラのレンズの向こうに、これまで沈黙を強いてきた、見えない他者たちを見据えて、語っている。したがって、これは証言者個人、インタービュアー、見えない他者たちの3者の間の対話の試みなのである。その3地点からなる構図のなかで、証言者たちは真剣勝負をしている。
福島の証言者たちに犠牲を強い、さらに沈黙を強いたのは私たちだ。私たち、多数者だ。証言者たちはインタービュアーに対して語っているようで、本当はそのようにして、そのようなやり方で私たちに向かって語っている。私たちは、私たちによって二重に犠牲にさせられた人々の、壮絶な痛みをわかることができるのだろうか。映画は、私たちにそれを問いかけている。
作品のタイトルは『福島は語る』である。沈黙というテーマを表に出せば、「福島が沈黙を語る」となるのではないか。実に、一連の土井作品のテーマは「沈黙」なのだと私は思う。沈黙監督と言ってもいい。土井さんはドキュメンタリー映画『沈黙を破る』で、2009年の石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、キネマ旬報ベストテン文化映画部門第1位を受賞された。この映画もまた、パレスチナ紛争のなかで「語られないこと」、つまり沈黙の、その深さに迫り、それを可視化した作品だった。単に紛争地の情景を撮影するのではない。紛争地の現場に行くことは簡単なことではないだろう。しかし、情景は現場に行けば目に見えるものだ。『沈黙を破る』はそうではない。土井さんは暴力の、見えない構造を映画という手段で可視化した。この映画も中東紛争についてのドキュメンタリーのなかで通常の次元を超えていた。今、ドキュメンタリー映画『福島は語る』は、原発メルトダウンの3.11から8年目となる2019年3月に公開されようとしている。それだけの時間を寝かせたからこそできた作品ではないかと思う。言葉の醗酵には必要な時間というものがある。映像の編集においても醗酵時間は必要だろう。ちょうど福島の酒造りのように……。2018年の全国新酒鑑評会で、福島県の酒は金賞を受賞した銘柄の数において6年連続日本一を達成した。今の仕事が一段落したら、また福島に酒を飲みに行こう、人に会いに行こう、そう思いながら、私は試写場から夕暮れの街に出て、いつもより確かな足取りで歩いた。
私が試写会で観た、劇場版は2時間50分。3.11に合わせて、東京では3月2日からその劇場版のロードショーが始まる。そのすぐ後、全国で一斉に上映するそうだ。それはいわゆる短縮版で、それとは別に5時間30分の長時間版が存在するそうだ。

なぜ『福島は語る』を制作したのか
監督 土井敏邦
言葉の映像化
この映画は、福島の被災者たちの“証言ドキュメンタリー”です。派手な動きがあるわけではありません。ひたすら、“語り”が続きます。観る人が単調で退屈だと感じて途中で投げ出すなら、この映画は失敗です。しかし“語り”に観る人が引き込まれ、最後まで観てくれる力があれば、この映画は意義があります。私はこの映画で、“言葉の力”に賭けてみました。
なぜ今、“言葉”なのか。原発事故から8年になろうとする現在の日本で、「フクシマ」は多くの人びとから「もう終わったこと」として忘れさられようとしています。2020年の東京オリンピックの話題に、社会の関心が高まるにつれ、その傾向は強まっています。
福島の為政者たちも、「風評被害の払拭」「復興」の名の下に、「フクシマ」の現実を覆い隠そうとしているようにも見えます。
しかし、「原発事故」によって人生を狂わされ、夢や未来を奪われ、かつての家族や共同体の絆を断ち切られ、“生きる指針”さえ奪われた被災者たちの“生傷”は癒えることなく、8年近くになる今なお、疼き続けています。
ただそれは、平穏に戻ったかのような現在の福島の光景からは、なかなか見えてきません。その“生傷”を可視化する唯一の手立ては、被災者たちが語る“言葉”です。この映画は、その“言葉”の映像化を試みた作品です。

福島の証言を残すこと
本作『福島は語る』の取材を開始したのは、私の前作『飯舘村―放射能と帰村―』の劇場公開から1年後の2014年4月です。きっかけは、この年の春、福島原発告訴団が東京・豊島公会堂で開催した「被害者証言集会」でした。800人の観衆で埋まったこの集会で、数人の被災者の方々が、自らの原発事故後の体験と心情を語りました。その一人ひとりの証言は聞く者の胸に迫ってくる切実な体験でした。その訴えを聞きながら、私は「被災者の方々のこれらの貴重な体験を、会場の800人にしか聞いてもらえないのはあまりに惜しい。原発事故の被災者たちの切実な声をもっと多くの人たち聞いてもらうために記録し残そう」と思いました。それがこの証言映画を作ろうと決心した直接の動機です。
実際に証言を集めようとするとき、真っ先にぶつかった問題はどうやって語ってくれる被災者たちを探すかです。私は、あの「被害者証言集会」を開いた福島原発告訴団の団長、武藤類子さんに相談し、告訴団のメンバーの中から紹介してもらうことにしました。武藤さんが紹介してくださった方々たちの取材を開始したのは2014年4月です。福島原発告訴団のメンバーの方々、そしてその方たちに紹介してもらった他の被災者の方々を私は車で訪ね回りました。その数は4年間で100人近くになりました。
しかしそれまでのインタビュー映像を粗編集してつないでみると、自分の胸にストンと落ちる記録映像ではありませんでした。“胸に染み入る深さ”がないのです。
原発事故後に自分や家族に起こった事象、今に至るまでの生活環境の変化、その中で抱え込んだ「問題」はある程度表現されていましたが、語る人の内面、“深い心の傷”“痛み”が十分に引き出せてはいませんでした。つまり「問題」は描けていても、その中で呻吟する“人間”が描き切れていなかったのです。

人間を描くこと
私は、1980年半ばからほぼ30数年にわたって“パレスチナ”の現場を取材し日本に伝えてきました。試行錯誤の長い取材体験と報道の中で学んだことの一つは、“伝え手”は現場で起きる現象や事件を描くことだけではなく、“人間”に迫り、伝えなければならないということでした。
中東・パレスチナのような「遠い問題」を日本人に伝えるには、私たちが描く現地の人びとの姿の中に、日本人である自分と同じ“人間”を見せていかなければなりません。観る人、読む人が「もし自分があの人だったら」「これが自分の息子だったら」と、自らをその相手に投影させる“人間”を突き出して見せなければなりません。そのためには“人間として普遍的なテーマ”に迫る必要があります。例えば「人が生きるとはどういうことか」「生きるために何が一番大切なのか」「人の幸せとは何か」「家族とは何か」「土地・故郷とは何か」「自由とは何か」「抑圧とは何か」「死とは何か」といったテーマです。それらが欠落し、現象や問題だけを伝えるのであれば、所詮、「自分とは関係のない遠い問題」でしかないのです。
私は「フクシマ」も同じだと思いました。
インタビューで聞き出す言葉が単に周囲で起こる現象や事件だけに終わってしまっては、「人間を描く」ことにはなりません。福島の原発事故がもたらした事象やその特殊性を突き抜けた“人間の普遍的なテーマ”に迫る言葉を引き出せていなかったのです。それは、証言者側の問題というより、彼らがなかなか言語化できずに心の奥底に沈殿させているその深い思いを引き出す私の “能力”の問題であり、私の“人の内面を見抜く目” “人間への洞察力”の問題でした。つまり“聞き手”の私自身の生き方、人間観、思想が問われていたのです。

「チェルノブイリの祈り」との出会い

そんな時、1冊の本に出会いました。2015年度のノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレクシエービッチ著『チェルノブイリの祈り』です。
この本は、事故から10年後に発表された事故被害者たちの証言集です。そこにはアレクシエービッチ自身の解説はありません。ひたすら被害者たちの生々しい語りが続きます。しかもそれは単なる「事実の羅列」ではありません。その言葉が、読む私の心に深く染み入るのです。「被害者の証言」だけの作品なのに、なぜこれほどまでに私は衝撃を受けたのか。なぜこれほど読む者の心を揺さぶる語りを聞き出せたのか。どうすれば「事故の緊急リポートにすぎず、本質はすっぽり抜け落ちてしま」(アレクシエービッチ)わないドキュメントが生み出せるのか。私の「フクシマ」取材の行き詰まりを抜け出すヒントがここにあるような気がしました。
この著書(岩波現代文庫版)の「あとがき」にジャーナリストの広河隆一氏が、著書の中でも最も感動的な証言の一つ、冒頭の消防夫の妻リュドミーラの語りについて書いています。
事故直後に現場の消火活動に駆り出され、致死量の数倍もの放射能を浴びた夫は、文字通り身体が崩れていきます。その夫に付きそい、必死に世話を続けたリュドミーラは原発事故についてではなく、ひたすら「どれほど夫を愛していたか」をアレクシエービッチに切々と語ります。広河氏はその証言とアレクシエービッチの力についてこう評しています。
「リュドミーラの力だけではないことは、私にはわかる。なぜなら私自身も昔彼女に会って話を聞いたことがあるからだ。しかし私が書き留めた言葉は、アレクシエービッチのそれとはまったく違っていた。私の記録には、輝きの片鱗も見られない。事実の羅列にすぎない。アレクシエービッチだからなしえたことがあったのだ。アレクシエービッチの仕事は、最も過酷な形で崩壊させられていく人間の姿を、生命の尊厳で書き留めていくことだったのだ。それは決して覆い隠すことで守られていく尊厳ではなく、言葉の極限まで語りつくしていきながら、守られていく尊厳だった」
「アレクシエービッチのこの本は、ドキュメンタリー文学の最高の傑作ともいえる力で驚くべき世界を伝えている。言葉とはこうしたことを成し遂げるために存在しているのか、と思うばかりだ。
その力を私自身も渇望している。戦争で、核被害の現場で、撮影する写真に求められるものも、それに似た力を必要としているのだろう。砲弾で叩き潰された体、放射能で焼けただれていく体、腐臭、そうした記憶が、言葉や写真の形で、尊厳ある伝え方をされるためには、どれほど心のたたかいが必要なのだろうか。それともそれはその人に備わった資質と呼ばれるものだろうか」
どんな過酷な事象や体験をも、「尊厳ある伝え方」で伝えていく。単に目の前に現れる、また語られる現象や事実を、ただ表象をなぞるのではなく、その本質と尊厳を見出す目。私が「フクシマ」取材に行き詰っていた原因はその欠落にあるのだろうか。それ以前に私は、「フクシマ」を伝えるためにこれまでに一体どれほどの「心のたたかい」をしてきただろうか。そもそも「その人に備わった資質」もないのに、「ないものねだり」をして能力を超えることを無理にやろうとしているのかも知れません。
しかし私は、ここでおずおずと引き下がりたくはないと思いました。「負けた。自分にはできない」と投げ出すことは、「心のたたかい」を放棄し自身の尊厳を放棄することに等しいことだからです。
こんな「備わった資質」もない私でも“伝え手”としてできることがあるはずです。「一人ひとりの人間が消えてしまったように」されていく国内の現状の中で、「個々の人間の記憶を残すこと」はこんな私でもいくらかはできるはずです。アレクシエービッチにはなれなくても、『チェルノブイリの祈り』ほどの記録は残せなくても、私なりに「フクシマの記憶と記録を残す」ことはできるはずです。『福島は語る』はそういう試行錯誤と暗中模索の中で、かたちとなった作品です。


監督プロフィール

土井 敏邦(どい としくに)
1953年佐賀県生まれ。ジャーナリスト。
1985年以来、パレスチナをはじめ各地を取材。1993年よりビデオ・ジャーナリストとしての活動も開始し、パレスチナやアジアに関するドキュメンタリーを制作、テレビ各局で放映される。2005年に『ファルージャ 2004年4月』、2009年には『届かぬ声―パレスチナ・占領と生きる人びと』全4部作を完成、その第4部『沈黙を破る』は劇場公開され、2009年度キネマ旬報ベスト・テンの文化映画部門で第1位、石橋湛山記念・早稲田ジャーナリズム大賞を受賞。次作となった『“私”を生きる』(2010年)は、2012年度キネマ旬報ベスト・テン文化映画部門で第2位。
東日本大震災後に制作された中編『飯舘村 第一章・故郷を追われる村人たち』(2012年)では「ゆふいん文化・記録映画祭・第5回松川賞」を受賞。また、2012年には、ビルマ(ミャンマー)から政治難民として日本に渡った青年を14年にわたって見つめた『異国に生きる 日本の中のビルマ人』で2013年度キネマ旬報文化映画第3位、文化庁映画賞文化記録映画優秀賞受賞。その他に『飯舘村 放射能帰村』(2013)、『ガザに生きる』全5部作(2014)など。著書は『アメリカのユダヤ人』、『沈黙を破る─元イスラエル軍将兵が語る“占領”─』(いずれも岩波書店)など多数。
土井敏邦 ホームページ
土井敏邦 ツイッター
土井敏邦 フェイスブック

制作クレジット
- 監督・撮影・編集:土井敏邦
- 整音:藤口諒太
- 朗読・題字:高橋長英
- 写真:森住卓
- 挿入歌:「ああ福島」李政美(作詞:武藤類子、作曲:李政美)
- 宣伝美術:野田雅也
- ウェブサイト:安藤滋夫
- 後援:城南信用金庫
- 配給:きろくびと、ピカフィルム
- 2018年/日本/カラー/170分

チラシ・ダウンロード【PDFファイル/1.3MB】
自主上映申し込み
- 自宅から本格的な上映会まで対応可能です。
- 小規模なグループや友人同士など、外部に呼びかけない仲間内での上映も可能です。
- 自分一人のための上映会も可能です。
- 映画館での上映を見逃された方やもう一度見てみたい方、家族や友人に見てもらいたい方など、お気軽にお問い合わせ下さい。
- DVDプレーヤーとテレビ(モニター)があれば上映できますので、ご自宅での上映会も可能です。
- DVDの上映ができれば、無料や低価格で借りるとができる地域の集会場や会議室、レンタルスペースなどでの上映も可能です。
- 下記上映料に合わせて、参加者の鑑賞料の金額は主催者が自由に設定できます。主催者が上映料と会場費を負担すれば鑑賞料を無料にすることもできます。
- 土井敏邦の講演依頼も募集しています。
【上映料】(1回上映につき)
- A: 10人未満:1万円
- B: 10人以上 50人未満:3万円
- C: 50人以上 100人未満:5万円
- D: 100人以上:500円 X 入場者数
上映の1週間ほど前に、DVDを郵送します。DVDは上映後に返却をお願いします。
【監督講演】
講演料など経費は、直接ご相談ください。
【申し込み/問い合わせ】
doitoshikuni@mail.goo.ne.jp
土井敏邦の他の作品の上映については 自主上映 申し込み案内 をご覧ください。映像作品のDVD通販については オンライン・ショップ をご覧ください。

上映情報
 『福島を語る』には【劇場版/2時間50分】と【完全版/5時間20分】があります。
『福島を語る』には【劇場版/2時間50分】と【完全版/5時間20分】があります。 の表記がないものは【劇場版】です。鑑賞の際はご注意ください。
の表記がないものは【劇場版】です。鑑賞の際はご注意ください。
映画館上映
- (上映終了分)
- 【2019年】
- 新宿K’s cinema 3月2日〜3月15日
- フォーラム福島 3月8日〜3月14日
- 佐賀シアターシエマ 上映延長 3月8日〜3月21日
- 渋谷ユーロスペース 3月9日〜3月22日
- 横浜シネマ・ジャック&ベティ 3月9日〜3月22日
- 名古屋シネマテーク 3月9日〜3月15日
- 京都シネマ 3月9日〜3月15日
- 大阪・第七藝術劇場 3月9日~3月15日
- 東京・アップリンク吉祥寺 3月11日
- 福岡・KBCシネマ1•2 3月11日、3月14日、3月31日
- 広島・横川シネマ 3月15日〜3月21日
- 大阪・シアターセブン 3月23日〜3月29日
- 札幌・シアターキノ 3月27日
- 福岡・KBCシネマ1•2 3月31日 アンコール上映決定
- 仙台チネ・ラヴィータ 4月5日~4月11日
- 札幌・シアターキノ 4月12日
- 東京・下高井戸シネマ 4月13日〜4月19日
- 札幌・シアターキノ 4月20日~4月26日
- [自主上映] 愛知県豊田市 つくラッセル 5月4日
- [自主上映] 東京都江戸川区「メイシネマ祭'19」小松川区民館ホール2F 5月5日
- 石垣島・ゆいロードシアター 5月11日〜13日
- 吉祥寺・ココマルシアター 4月27日〜5月10日 、上映延長5月12日、5月13日、5月15日 上映 再延長 5月18日、5月20日〜5月22日
- 兵庫・元町映画館 6月23日、6月30日
- 山口・山口情報芸術センター 7月18日, 19日, 21日, 25日〜27日
- 新潟・シネ・ウインド 8月3日
- 鹿児島・ガーデンズシネマ 8月4日
- 三重・伊勢進富座 8月31日、9月1日
- 熊本・Denkikan 9月7日/8日
- 東京・文化庁映画賞 受賞記念上映会 11月2日
- 【2020年】
- 長野・松本CINEMAセレクト 1月11日
 東京・第9回江古田映画祭 2月29日
東京・第9回江古田映画祭 2月29日 佐賀・シアターシエマ 3月7日
佐賀・シアターシエマ 3月7日- 神奈川・あつぎのえいがかんkiki 3月7日~3月13日
- 長野松竹相生座・ロキシー1•2 3月7日〜3月20日
 渋谷・ユーロスペース
渋谷・ユーロスペース
3月10日
3月11日- 3月10日上映後トーク
榊原崇仁さん(東京新聞特別報道部記者)/高橋長英さん(俳優/本作朗読•題字)/土井敏邦監督 - 3月11日上映後トーク
おしどりマコ・ケンさん(芸人•記者)/村田弘さん(原発被害者団体連絡会幹事/本作出演)/土井敏邦監督
- 3月10日上映後トーク
 横浜・シネマ・ジャック&ベティ 3月13日
横浜・シネマ・ジャック&ベティ 3月13日
- 上映後トーク:高橋長英さん(俳優/本作朗読•題字)/土井敏邦監督
- 札幌・シアターキノ<アンコール上映> 3月13日
- 福井メトロ劇場 3月14日〜3月20
 大阪・シアタ―セブン 3月20日・21日
大阪・シアタ―セブン 3月20日・21日 広島・横川シネマ 3月31日・4月1日
広島・横川シネマ 3月31日・4月1日 フォーラム福島 5月17日
フォーラム福島 5月17日 フォーラム福島 12月13日
フォーラム福島 12月13日- 【2021年】
 日比谷図書文化館コンベンションホール 2月27日
日比谷図書文化館コンベンションホール 2月27日
- 対談・伊勢真一監督×土井敏邦
 長野・相生座・ロキシー 3月14日
長野・相生座・ロキシー 3月14日 東京・下高井戸シネマ 3月11日(木)・12日
東京・下高井戸シネマ 3月11日(木)・12日
自主上映
予定は変更になる場合があります。
参加される場合は必ず主催者発表の情報をご確認下さい。
特にことわりがない限り 予約不要 で どなたでも参加できる 上映会です。
【2020年】
- 仙台 せんだいメディアテーク
1月11日(土)10:00/ 13:20/ 16:40(3回上映)- 参加料金:前売り1000円、当日1300円(学生500円・高校生以下 無料)
- 前売り券:メディアテーク1階 Kaneiri Museum Shop 6
- 主催:子どもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換をめざす女性ネットワークみやぎ
- 大阪大学 人間科学研究科 東館
1月31日(金)17:00~20:30
※大阪大学人間科学研究科に所属する学生又は教職員向けの企画- 参加料金:無料
- 主催:大阪大学 未来共創センター
- 千葉 浦安音楽ホール・ハーモニーホール
2月15日(土) 18:40- 入場料:一般・シニア・大学・専門 999円/サポーター会員 799円/高校生以下 500円
- 事前予約優先
- 主催:浦安ドキュメンタリーオフィス
- 連絡先:070-5459-9205
- 札幌 札幌北部教会
3月5日(木)10:00(開場9:40)
- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 小樽 生涯学習プラザ レピオ
3月7日(土)13:30(開場13:00)- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 苫小牧 苫小牧市民活動センター会議室2
3月7日(土)13:00- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 鳥取 わらべ館いべんとほーる
3月7日(土)9:30/14:00 2回上映- 参加料金:前売り800円/当日1000円
- 主催:とっとり(エネルギーの未来を考える会)、脱原発しょいやinとっとり
- 静岡 掛川市生涯学習センター

3月7日(土)- 主催:『福島は語る』をみる会
- 問い合わせ:sihoko@mbr.nifty.com
- 江別 野幌公民館ホール
3月8日(日)13:30/17:00(2回上映)- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 東京 明治学院大学 白金校舎

3月10日(火)- 主催:明治学院大学 キリスト教研究所 キリスト教主義教育研究プロジェクト
- 連絡先: kiriken@chr.meijigakuin.ac.jp
- 札幌 聖公会札幌キリスト教会

3月14日(土)- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 旭川 建設労働者福祉センター(サン・アザレア)3階ホール

3月14日(土)- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 夕張 夕張拠点複合施設「りすた」

3月14日(土)- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 福岡 サンレイクかすや(糟屋郡)

3月14日(土)- 主催:「福島は語る」上映会実行委員会
- 連絡先はチラシを参照→チラシ【PDFファイル】
- 島根 食の杜内 忠庵(かやぶきの屋根となり)
3月15日(日)10:00/14:00(2回上映)
3月16日(月)10:00- 参加料金:前売り 1200円/当日 1500円/学生 500円/高校生以下 無料
- 主催:あげ!そげ?はっけんぐみ
- 岡山 県立図書館 デジタル情報シアター

3月15日(日)- 主催:子ども未来・愛ネットワーク(担当:片岡)
- 連絡先: kiitos2612@gmail.com
- 沖縄 日本聖公会 沖縄教区 三原聖ペテロ聖パウロ教会
3月15日(日)13:30- 参加料金:100円
- 主催:日本聖公会 沖縄教区 災害支援室
- 連絡先: isaac@anglican-okinawa.jp
- 備考:どなたでも参加できますが教会での上映につき同会場でお祈り等の宗教行事も行われます
- 滋賀 コラボしが21(膳所)
3月15日(日)13:45~16:45- 参加料金:無料
- 主催:滋賀県保険医協会
- 連絡先:TEL 077-522-1152/FAX 077-525-3093
- 東京 狛江市中央公民館

3月21日(土)- 主催:狛江の放射能を測る会
- 連絡先: toiawase@hakarukai.clean.to
- 千葉 千葉市生涯学習センター
3月25日(水)13:15~16:15- 参加料金:500円
- 主催:わかば「お茶っこ」しよう会
- 山口 防府市地域協働支援センター
3月28日(土)13:30~16:30- 料金:前売り1000円/当日1200円(高校生以下 無料)
- 主催:エコシフトほうふ
- 連絡先: 0ta35935@gmail.com (村田)
- 登別 市民会館視聴覚室
3月28日(土)13:30(開場13:00)- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 室蘭 中小企業センター視聴覚室
3月29日(日)13:30(開場13:30)- 主催:「福島は語る」北海道連続上映会
- 共催:カトリック札幌地区正義と平和協議会、日本基督教団北海教区平和部門委員会、日本聖公会北海道教区
- 連絡先:企画詳細チラシ をご覧ください。
- 福岡 聖パウロ教会
5月7日(木)

- 参加料金:無料(会場にて自由献金)
- 主催:日本聖公会九州教区伝道部
- 連絡先: gfrmc051@yahoo.co.jp (安村)
- 青森 弘前文化センター大ホール
5月30日(土)13:30- 参加料金:大人1000円、大学生・障がい者500円
- 主催:After311脱原発弘前映画祭実行委員会
- 連絡先: takenami1717@gmail.com
- 東京 小金井 宮地楽器ホール
7月25日(日)

- 主催:小金井に映画館をつくろう
- 連絡先:ones.eyes.fest@gmail.com
- 島根 米子コンベンションセンター 小ホール
9月20日(日)13:30~ (13:00開場)- コロナ対策のため事前に予約が必要です
- 予約・連絡先:arisaema35@outlook.jp(山中)
- 参加料金 1000円
- 主催:さよなら島根原発ネットワーク
【2019年】
- 岡山・瀬戸内市 保健福祉センター ゆめトピア長船
5月26日(日)13:00(12:30開場)- 入場料:1000円
高校生以下、および東日本大震災に伴う避難移住者は無料 - チケット販売:天然酵母パン屋「オぷスト」
- イベント紹介ページ
- 主催:せとうち交流プロジェクト
- 後援:岡山県、瀬戸内市、瀬戸内市教育委員会、山陽新聞社
- 入場料:1000円
- 横浜国立大学
5月30日(木)- 横浜国大生向け企画
- 6月6日(木)土井敏邦監督 講演と質疑
- 主催:高橋ゼミ〔ジャーナリズム〕
- 長野・上伊那郡 中川文化センター
6月16日(日)13:30(13:00開場)- 前売り:1200円 /当日券:1500円
高校生 500円、中学生以下無料 - チケット販売:平安堂プレイガイド、風の谷絵本館、アートハウス
- 主催:福島を語る実行委員会
共催:ドキュメンタリー映画を観る会
- 前売り:1200円 /当日券:1500円
- 山形・米沢市 置賜総合文化センター
6月22日(土)14:00- 参加料金:1000円
- 主催:さようなら原発 米沢代表 高橋寛
- 連絡先: kansan@tempo.ocn.ne.jp (沼澤)
- 神奈川・相模原市 篠原の里センター
6月26日(水)18:00- 主催:しのばらんど
- 連絡先:電話 080-1088-6650(後藤)
- 参加費:1000円
- 千葉・南房総市 花の谷クリニック
6月30日(日)10:00〜17:00- 完全版(5時間30分版)の上映
- 途中、お昼休憩と15分程度の休憩を2回はさみます
- 参加料金:2000円
- 共催:スープのよろずや「花」 /未来をつむぐ安房の会
- 茨城・牛久市 中央生涯学習センター視聴覚室
6月30日(日)13:30~16:30- 参加費:500円
- 主催:環境学習同好会
- 岡山市・北区 奉還町4丁目ラウンジ・カド
7月7日(日)14:00- 参加費:1000円
- 主催者:谷合裕子
- 福島・田村郡三春町 えすぺり
7月16日(火)18:00- 参加費:前売り1000円・当日1200円(小学生以上が対象)
- 連絡先: ichikaraya088@gmail.com (大河原)
- 東京 葛飾区立石地区センター
7月21日(日)14:00- 別館2階 集会室
- 上映協力費:1500円
- 主催:NPO法人かつしか子ども劇場
- 連絡先: katusika.kogeki@gmail.com
- 山形 長井市置賜生涯学習プラザ
8月4日(日)時間未定- 入場料:700円
- 主催:「福島は語る」を観る会
- 連絡先: tomotomoko128@gmail.com (森田)
- 東京 まちだ中央公民館(町田市生涯学習センター)
10月5日(土)13:00~17:00(上映後、話し合いの時間を予定)- 町田市福島県人会・会員対象の企画
- 無料
- 主催:町田市福島県人会
- 島根 松江市民活動センター交流ホール
11月2日(土)2回上映(時間未定)- 参加料金:未定(1000円〜1300円程度予定)
- 主催:「福島は語る」上映実行委員会、島根原発1・2号機差し止め訴訟原告団
共催:松江キネマ倶楽部、人権パッチギの会松江、中国電力・島根原子力発電所3号機の運転を止めさせる訴訟の会 - 連絡先: ashi@lapis.plala.or.jp(芦原)
- 神戸 市立総合福祉センター
11月24日(日)13:30〜16:00- 参加費:無料
- メールにて予約可能
詳しくは下記、主催者のサイトをご覧ください - 主催:NPO法人 COM総合福祉研究所
- 福岡 糸島市・健康福祉センター「あごら」視聴覚室
11月24日(日)13:30- 参加料金:1000円(学生、障がい者 無料)
- 主催:脱原発!いとしまネットワーク
- 問い合わせ詳細
- 東京 多摩市・ベルブホール
11月29日(金) 16:00〜19:00 (途中休憩あり)- 「映画祭TAMA CINEMA FORUM」内での上映
- 料金:前売り 1500円/当日 1800円
- 主催:TAMA映画フォーラム実行委員会
- 四日市 四日市市総合会館
12月1日(日)13:30~16:30(開場13:00)- 参加料金:一般1000円、高校生以下500円
避難者の方無料 - 主催 脱原発四日市市民の集い
- 連絡先:090-7687-95408(大野)
- 参加料金:一般1000円、高校生以下500円
- 香川 高松市男女共同参画センター第3会議室(たかまつミライエ)
12月7日(土)13:00~16:30- 参加料金 : 500円(学生無料)
- 託児あり(無料・ただし11月15日までに要申込)
- 企画・運営:NPO法人福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト&自由席
- 主催:2019高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会
- 連絡先: ZVF05007@nifty.com



