日々の雑感 235:
山形国際ドキュメンタリー映画祭/報告(6)
2011年10月13日(木)
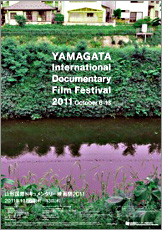
この映画祭で私はたくさんのドキュメンタリー映画関係者と出会い、多くのことを教えられた。その1人が映画『チョコラ』の監督、小林茂さんだった。この映画の編集と製作を担当した秦岳志(はた たけし)さんは、私の映画『沈黙を破る』を私と共に編集した仲間である。その秦さんを通じて、私は数年前に小林さんと出会った。しかし、ゆっくり話を聞く機会は今回が初めてである。途中で飛び出してしまった映画を批判し、「なぜこんな映画が選ばれたのだろう」と、わかったふうなことを言う私の“ドキュメンタリー”観の狭さと浅さに危うさを感じたのだろう、小林さんは私のその狭い“ドキュメンタリー映画”観を諌めるように、山形国際ドキュメンタリー映画祭について私に語ってきかせた。アジアのドキュメンタリー映画作家を育てる重要な役割を担ってきたこと、この映画祭はあらゆるタイプのドキュメンタリーを受容し見せていく映画祭であること、そして彼自身にとってこの映画祭がどれほど大切な催しであるかを小林さんは切々と語った。とりわけ私の心に残ったのは、カメラマンとして制作に関わった名作『阿賀に生きる』とこの山形映画祭との関わりだった。佐藤真監督や小林さんたち制作者たちは、まだ編集途上の『阿賀に生きる』の粗編が第1回の山形映画祭で上映してもらうことになり、大人数でホテルに泊まる金もない小林さんや佐藤さんたち制作者たちは橋の下にテントをはって寝泊まりし、この映画祭に通った。だが、上映された『阿賀に生きる』はさんざんな酷評を受けた。衝撃を受けて阿賀に戻った佐藤さん、小林さんらはいったん作品を解体し、最初から組み立てなおす決心をする。撮った映像を再分類化し編集をやりなおし、足りない映像を追加撮影し、2年後、まったく違った作品に仕上がった。次の第2回山形映画祭に正式な招待作品となった『阿賀に生きる』は、高い評価を受けた。その後、この映画は国内外で数々の賞を獲得していくことになる。
「『阿賀に生きる』はこの山形映画祭に育てられたんです」と小林さんは言う。「だから私にとってこの山形映画祭はとても大切な場だし、どんな部門でもいい、自分の作品がここで上映してもらうことはなによりの喜びだし、誇りです」

もう1人、この映画祭で出会った巨匠のことを書いておきたい。大津幸四郎さんは、土本典昭(つちもと のりあき)作品、小川紳介作品のカメラマンとして広く知られ、私もその作品のいくつかは拝見してきた。その大津さんの撮影の姿勢、思想を映画祭最終日のクロージング作品『まなざしの旅 土本典昭と大津幸四郎』(代島治彦 監督)のなかで初めて知った。撮影者としてその対象に向かう基本的な“姿勢”を教えられた思いがして、深い感銘を受けた。お別れパーティーの席で、その大津さんと話をする機会があった。
私は『まなざしの旅』の中に登場する、あるシーンについて自分の率直な感想を大津さんに伝えた。それは水俣の胎児性患者の女性が、熊本大学の原田教授に海辺で相談するシーンである。それは胎児性患者として障害を一生かかえて生きなければならない自分の人生について悩み、泣きながら原田教授に打ち明ける重い場面である。大津さんは、その女性を数メートル離れた背後から撮影している。もちろんその女性にも、原田教授にも撮影の了承は得ていたと大津さんは言う。ならば、なぜ離れた背後からではなく、女性の正面に回って、泣くその顔をアップで撮ろうとしなかったのか。私なら、そうする。その方が“より強い絵”になるからだ。しかし大津さんは「カメラが2人に近づくことで、2人の間に漂う緊密な空気を壊したくなかった」と言った。そしてこう付け加えた。
「それに、あの女性の気持ちに寄り添ったら、正面に回り込む気持ちになれなかった」
私は“寄り添う”という言葉にはっとした。“カメラを向ける相手の気持ちに寄り添って撮る”ということ。これまで長年、撮影をしてきた私に、それができていたのか。“寄り添う”ために、あえて“強い絵”を撮りたいという衝動と誘惑を抑え込む自制心が自分にはあったのか。戦場などで悲惨なシーン、“強い絵”になる場面に出くわしたとき、私は多くの場合、その誘惑を抑えきれなかったことを告白しなければならない。
「撮影に、いちばん大切なことは何ですか」と私は大津さんに質問を重ねた。すると大津さんは、「撮る相手が人間としていちばん美しい姿、人間として尊厳がいちばん出ている姿を撮りたいと思っている」と答えた。それは映画『水俣─患者さんとその世界─』の中にあらわれている。ユージン・スミスの写真『裸の母娘像』で有名になった上村智子さんの映像だ。スミスの写真のような痩せ細りあばら骨が浮き出た智子さんの裸体や、痙攣して目がむき出した、「水俣病患者」を象徴するような姿ではなく、人間としていちばん輝き、尊厳のある姿を撮ることにこだわった大津さんと土本監督の姿勢は、その映画の中で、家族に囲まれ微笑んでいる智子さんの姿を描くことに象徴的に表れている。
撮る相手に寄り添い、その人の尊厳を損なわないように心を砕く──カメラマンの巨匠・大津幸四郎さんからドキュメンタリーの撮影の極意を教えてもらったような気がする。
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。
