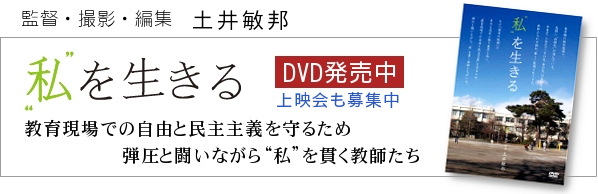日々の雑感 251:
『“私”を生きる』の劇場公開に寄せて(2)
2011年1月17日(火)
この映画を制作する動機、経緯、こめた思いは『“私”を生きる』のサイトの「監督のことば」に書いた。
実は、当初この映画は根津公子さんだけで制作するつもりで、2007年2月から2年ほど根津さんの取材・撮影を続けていた。ただ当初から念頭に置いていたのは、「この映画を『日の丸・君が代』問題の運動の映画にはしない」ということだった。「運動の映画」とみなされると、運動の当事者・支援者の方々、教育関係者の人たちには観てもらえても、一般の人たちの間には広がって行かないと思ったからだ。私がいちばん観てほしいのは、そういう“関係者”ではなく、教育現場とはまったく無関係な一般の人たちである。そのためには「運動」ではなく「生き方」を伝えることだと思った。

「君が代・不起立」のシンボルとしてすでに有名な根津さんも、これまですでに知られている「活動家の顔」とは異なる“顔”を描きたかった。だから「集会や抗議活動の中の根津さん」の映像はすべてカットした。「映像の中では、根津さんにはマイクを握らせない」と決めたのだ。それは最初に根津さんと会ったとき、根津さんの魅力は集会や抗議行動の中でマイクで訴える時のあの「強い根津さん」ではなく、日常の柔らかな表情と語りの中にあると気付いたからである。日常の生活中での“普段着”の根津さん、子どもたちにとってほんとうの教育を実践したいともがく教育者として根津さん、そのために弾圧を受け打ちひしがれ、自死まで考えた根津さん、そして母親として子どもたちの幸せを願う根津さん……。これまであまり知られてこなかった根津さんの“顔”を丹念に積み重ねれば、この人の人間として魅力は伝えられるはずだと思った。
それでも、やはり根津さんから「『君が代・不起立』の根津」のイメージは払しょくされない。ならば、根津さん独りのドキュメンタリーにするのではなく、他の登場人物を組み合わせることで、その壁を乗り越えられるのではないかと考えた。そこで私の視野に入ったのが佐藤美和子さんだった。

拙著『沈黙を破る』(岩波書店・2008年)の執筆の過程でお世話になった精神科医・野田正彰氏から1冊の著書をいただいた。それは『子どもが見ている背中─良心と抵抗の教育─』(岩波書店)という本で、その3分の1ほどが佐藤美和子さんに関する記述だった。キリスト者として「君が代」伴奏を拒否することで心身ともに追い込まれていく一教員を精神科医の眼で詳細に描いたその文章に引き込まれた。読み終えたとき「この人を映像で描きたい」と思った。それが佐藤美和子さんとの出会いだった。
いつもの私の取材パターンだが、まずカメラを三脚の上に固定し、その横で佐藤さんの話をじっくり聞いた。生い立ち、家族、音楽教員になるきっかけ、そして学校現場で起こったこと……。そのインタビューは根津さんの場合と同じように、私のドキュメンタリーの柱になった。ただドキュメンタリーは活字とは違い、インタビューだけでは成立しない。音楽教員である佐藤さんには生徒たちに音楽を指導している映像がどうしても必要だ。しかし、学校内での撮影は校長の許可なしではできないし、都教委に批判的なこの映画の撮影を校長が許可するはずもない。幸い、校外での合唱大会で指揮する佐藤さんと歌う子どもたちの交流の映像は撮影できた。これは音楽教師・佐藤さんの“顔”を象徴する大事なシーンとなった。
佐藤さんのパートでもう1つ重要なシーンは、亡くなったお父さんの告別式である。それは「天皇制につながる『君が代』」の伴奏を拒否する佐藤さんの思想の原点が映し出されているからだ。キリスト者でありながら、天皇制の下で軍人としてビルマへ侵略し闘ったことへの深い反省から、戦後、牧師として平和運動に関わり続けた父親。その姿を見ながら育った佐藤さんの体験が、現在の佐藤さんの思想の原点にあることをこの告別式で観客は知ることになる。

根津さんと佐藤さんの撮影を終え、映像を編集し並べてみた。たしかに厚みが加わった。しかし2人とも「君が代」問題が背景にあるから、どうしても「『君が代』問題の映画」のイメージは払しょくできない。その問題を解決するには、「日の丸・君が代」問題とは異なる問題で闘い、教育現場で“私”を貫く教員が必要だった。思いあぐねていたときに、ある月刊誌に掲載された都立高校の校長・土肥信雄さんの人物ルポと出会った。「この人だ」と思った。
土肥さんに加わってもらうことで映画に厚みが加わったもう1つの点は、学校現場が撮れたことである。佐藤さんと根津さんのパートで一番苦労したのは教員である2人と子どもたちとの接点がなかなか撮れないことだった。学校の中での撮影が難しいからだ。しかし土肥さんの場合、「校長権限」で学校の中での土肥さんと生徒たちとの交流シーンが自由に撮影できた。それは土肥さんの人柄や教師像、教育観を表現するのに欠かせないシーンとなっている。
この映画を「運動の映画」にしないためにも、登場する3人が何よりも“教師”であることをきちんと描かなければならないと思った。どんなにその主張が立派でも、まず本職である“教師としての本来の仕事”がきちんとできていなければ、その言動は観る人の共感を呼ばない。教師として立派な人たちであることを観る人に伝えるためには学校現場での先生たちと生徒との接点が描かれていなければならない、しかし根津さんは停職処分中で学校にも入れず、子どもたちとの接点が描けない。どうすれば“教師・根津公子”を表現できるか。思い悩んだ末に浮かんだのが、根津さんが家庭科の授業で使っていた手書きの“教科書”と、教え子や同僚によって根津さんの“教師像”を語ってもらう証言であり、根津公子さんが「理想の教育ができた」と言う石川中学校での体験談だった。
この映画『“私”を生きる』は私の前作『沈黙を破る』と同様、“語り”が柱になっている。それは私が活字ジャーナリストとして出発していることに起因している。相手からじっくり話を聞き、相手の本音を引き出していく、その言葉を丁寧に紡んで文章にしていく──それが活字ジャーナリストとして私が長年やってきた手法だった。それは映像の世界に主軸を移してからも、基本的には変わっていない。
ただこの映画で発見したのは、同じ語りであっても、部屋の中で三脚を立ててインタビューすることと現場に立って語ってもらうこととには大きな違いがあるということだった。例えば佐藤さんの場合、国立第2小学校での体験は部屋の中での最初のインタビューの中で聞いてはいた。しかし実際、その学校の校舎を前にしたとき、佐藤さんは事務所でのインタビューでは語らなかった、「屋上から飛び降りることも考えた」当時の思いを初めて告白した。“現場”が佐藤さんに当時の心情を呼び起こさせたのだ。
根津さんの場合もそうだった。心に深い傷を負った多摩中学校の現場に立ったとき、「自死が頭に浮かんだ」と語った。これまで子どもにさえ語ったことのない秘めた過去だった。「強い根津公子」像からは想像もつかないその言葉とその時の根津さんの表情をカメラに収めながら、私は強い衝撃を覚えたことを思い出す。“現場に立つ”ことの意味を私は改めて思い知った。
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。