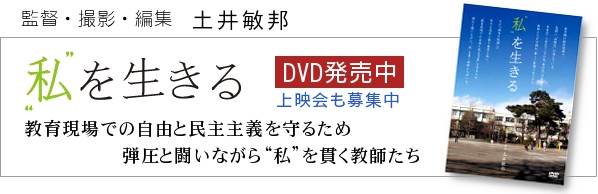日々の雑感 288:
還暦を迎えて(1)還暦の“プレゼント”
2013年1月14日(月)

(写真:飯舘村の長谷川健一・花子夫妻にいただいた、由緒ある綿津見神社の還暦祝いの「お札」。長谷川夫妻も還暦なので、飯舘村の長谷川家で、夫妻と私と連れ合いの4人で、3人の還暦のお祝いをした/2013年1月5日)
1月8日、60回目の誕生日を、取材先の東北・仙台のアパートの1室のシュラフの中で迎えた。咳き込んでよく眠れなかった。まだ外が暗い午前5時ごろ起き、30分後には、粉雪が舞い散る暗闇の中を、横浜に向かって車を走らせていた。暗闇の中、高速道路を走る。先が見えない道路を100キロ前後のスピードで走るのは怖い。しかも数分ごとに激しく咳き込み、そのたびに喉に激しい痛みが走る。最悪の体調での運転。しかし一時も早く、家に帰り、薬を飲まなければ、「風邪」は悪化するばかりだ。あたりが明るくなると、「自分の運転技術の限度」と決めている120キロ前後で車を走らせた。高熱と激しい咳、運転の休憩でサービスステーションで車から降りると、足元がふらついた。目を閉じると、白い星のようなものがいくつも回っている。6時間近い必死の運転の後、無事に自宅に辿り着いた。しかしもう荷物を車から降ろす気力も体力もなく、咳止めなど風邪薬を飲むと、倒れ込むように布団の中にもぐった。中華街で祝うはずだった「還暦の誕生日祝い」は、結局、中止。連れ合いが家で作ってくれた好物の料理もわずかに手をつけただけでまた布団に戻った。
翌日、ふらつく身体で自転車に乗って、かかりつけの港町診療所へ向かった。体温は38・5度。下された診断は「インフルエンザA型」。「1週間は外へ出てはいけません。家でもできるだけ家族との接触は避け、寝室も食器もトイレも別にしてください」。
このようにして、連れ合いとの「家庭内“別居”」の生活が始まった。仕事部屋に布団を持ち込み、そこで寝起きし、朝晩の食事の時は、「できたよ」という連れ合いの声がかかると、「独房」を出て、私一人分の食卓が並ぶリビング・ルームへ。連れ合いは少し離れた台所の奥から、マスクとゴム手袋姿で、黙々と食べる私の様子をじっとうかがっている。まるで、重症のコレラや赤痢患者を目の前にしたような警戒ぶりである。その姿に、映画『希望の国』に登場する、放射能汚染を怖れる妊娠中の若妻が宇宙服のような防護服に身をまとい病院の中を歩く姿を思いだした。
「そうよ。インフルエンザはコレラや赤痢と同じ『法定伝染病』なのよ」と台所の奥から連れ合いが言う。妻にさえ「差別され疎外され」ているようで悲しくなったが、しかし彼女の事情を思えば仕方がない。教師として毎日子どもを相手にする彼女に私のインフルエンザが感染したら、子どもたちにも感染させてしまう。彼女はそれをいちばん怖れ、私を「疎外」せざるをえないのだ。
生まれて60年間、私は「インフルエンザ」というものを体験したことがなかった。症状は風邪とほとんど変わらないこの病気だが、これほど辛い病気だと、まったく想像もしなかった。いちばん辛いことは、他人との接触を一切禁じられてしまうことだ。予定していた仕事の打ち合わせや撮影もすべてキャンセル。買い物にも行ってはいけない。1か所にじっと留まることが大の苦手の私には、狭い部屋に「隔離」されることは、ほとんど“拷問”である。しかも「早い回復には、寝るのが一番」と医者に言われ、一日中、布団の中にいる。眠れないのに、じっと布団の中に横たわっていなければならないのも、私には耐えがたい苦行だった。
ただ、悪いことばかりではなかった。病床で、退屈紛れに手にした『この国はどこで間違えたのか─沖縄と福島から見えた日本』(内田樹・小熊英二ら著/徳間書店)と『戦後史の正体』(孫崎享・著)の2冊は、私の今の仕事、今後の仕事の方向性に重要な示唆を与えられた。今まさに私は、“パレスチナ”“フクシマ”“オキナワ”を結びつける映像ドキュメンタリー・シリーズのプロジェクトを進めている最中だったからだ。近い将来、この2冊の本から学んだことをコラムに書き記したい。

もう1つ、仕事もできない「隔離」生活に意気消沈していた私に、“小さな光”のようなニュースが飛び込んできた。昨年1月から東京・渋谷を皮切りに全国で劇場公開した私のドキュメンタリー映画『“私”を生きる』が、「キネマ旬報2012年文化映画ベスト・テン」の第2位に選ばれたという知らせだった。
私の映画が最終選考に残っていることは、配給担当の中山和郎さんから聞き知っていた。もし運良く10位以内に入ればうれしいし、今後の映画制作の励みになるなと思ってはいた。正直、あの映画は、上位を狙えるほどのクオリティーはないと制作した私は自覚していた。取材・撮影・編集・製作をすべて私独りでやってきた。登場人物の3人の教師たちの“人間としての魅力”、“生き方の魅力”には確信と自信があり、それが観客にストレートに伝われば、この映画は観る人の心を動かせるという自信はあった。しかし問題は、作り手の技量であり、表現力である。撮影も編集も、プロのカメラマンや編集マンの人に比べたら、技量的に劣っていることは他人に指摘されるまでもなく、十分自覚している。ただ、その映像で何をどう伝えたいかは、誰よりも私自身がいちばんわかっている。しかも撮影と編集による表現のなかで、第三の表現者が加わることで生じがちな意思疎通の齟齬はありえない。「これを伝えずにおくものか!」という怒りを伴う情熱を監督の私ほど強く抱いている者もいまい。それらによって、技量のハンディをどこまで乗り越えられるかが勝負だと思っていた。
それにしても、「日の丸・君が代」問題、「天皇制」に触れるこの映画が一般の劇場公開できるとは私は考えていなかった。まず劇場側が右翼側からの攻撃を怖れて上映をためらうだろうと思ったのである。だから、完成した作品の公開形態として、当初からDVD販売と自主上映というかたちを取った。幸い、教育問題に関心のある人たちを中心に、DVDは地道にではあるが、じわじわと広がっていった。
劇場公開が決まったのはDVD販売を初めてから1年半も経ってからだった。それも、たまたま渋谷の劇場で1月の上映予定に空きができ、それを埋めるかたちで『“私”を生きる』の上映がその1ヵ月ほど前にあわただしく決まった。しかし劇場公開が始まると、1日1回のモーニング上映だったが、観客数は1週間ほどで1000人を超えた。登場人物である根津公子さんや土肥信雄さんの裁判の判決がメディアの注目を浴びる時期と重なったこともその「追い風」になった。
それにしても、2012年度のドキュメンタリー映画界は、『隣る人』や数々の「震災関連の映画」にも話題作も少なくなかったのに、単独制作者による手作りの地味な映画『“私”を生きる』が、伝統ある映画賞で第2位というのは、ちょっと出来過ぎのような気もする。
私はこの吉報を、「これまでの君のドキュメンタリー映画の作り方は間違っていないから、そのスタイルと“思い”で続けなさい」という、“励ましのメッセージ”だ受け止めた。
「こんなやり方でいいのか」「独りよがりの間違った方向へ向かっているんじゃないか」という不安と毎日闘いながら、私は独り、しこしことドキュメンタリー映像を作り続けてきたからだ。賞状も賞金もない「ベスト・テン第2位」だが、私にとって最高の“還暦プレゼント”である。
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。