日々の雑感 304:
山形国際ドキュメンタリー映画祭(2)
2013年10月17日(木)
- 『空低く、大地高し』
- 『チョール 国境の沈む島』
- 『みんな聞いてるか!』
『空低く、大地高し』
Boundary
タイ、カンボジア、フランス/2013/タイ語、クメール語/カラー/96分
監督:ノンタワット・ナムベンジャポン Nontawat Numbenchapol
『空低く、大地高し』(タイ)はタイ・カンボジア国境を描いた映画だったが、私には何を伝えたいのかまったく理解できず、観続けるのが辛い映画だった。我慢して観終わったとき、「私の貴重な時間を返してくれ!」と叫びたい衝動に駆られた。
『チョール 国境の沈む島』
Char . . . The No-man's Island
日本、インド、イタリア、ノルウェー、デンマーク/2012/ベンガル語、ヒンディー語/カラー/88分
監督:ソーラヴ・サーランギ Sourav Sarangi
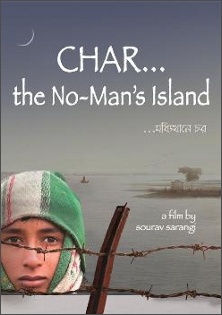
同じく国境を描きながら、『空低く、大地高し』と対照的だったのが、『チョール 国境の沈む島』である。監督は、4年前、私がこの映画祭で観て深く感動した『ビラル』の監督、ソーラヴ・サーランギだった。
インドとバングラディッシュの国境となっているガンジス川は、サイクロンのたびに沿岸の土地が侵蝕され、村々も消滅してしまう。しかもインドが上流にダムを建設したことで、ガンジス川は流れを大きく変えた。サーランギ監督は、沿岸の侵蝕によって土地を奪われていく人々に注目し、2002年にインド側の沿岸の村を訪ね、取材を開始した。しかし2005年から映画『ビラル』の撮影・制作のために3年間、取材は中断してしまう。その間も、土地の侵蝕によって生活を奪われる住民たちの姿がずっと脳裏から離れなかった。2008年、現地に戻ると、風景は一変していた。以前訪ねた村は消滅し、ガンジス川には大きな中州(チョール)が生まれていた。かつて出会った村人たちは、行き場を失い、そのチョールに住み着いていた。
サーランギ監督はそこでルベルという少年と出会う。映画はこの少年とその家族、少年の友人たち、そして村人たちの生活を丹念に追ったドキュメンタリーである。
両国の国境線がちょうど中州の上を通っているため、この島への立ち入りは禁止。ここに住み着いた住民の移動の自由も厳しく制限され、両国の警察の監視の目が光っている。住民たちは生きていくために、インドから米や薬を密輸して生活の糧を得る。少年たちも家族を支えるために自転車に山のような米袋を乗せ、川を渡る。ルベルもそういう少年の1人だ。父親は病気で重労働ができない、姉は持参金が準備できず、婚約者から結婚解消を迫られる、そんな家族の大黒柱はまだ幼い少年のルベルだ。学校で勉強したいが、両親は稼ぎが減るから学校を辞めろと迫る。しかし勉強がしたいルベルは精一杯、抵抗する。そんな家族の言い争いを、カメラはじっと見つめ記録する。まるで撮るサーランギ監督が存在しないかのように、日常の家族の裸の姿が淡々と描かれる。それは前作『ビラル』で見せたサーランギ監督作品の特徴だ。貧困にあえぎながら生きる家族の中にまるで透明人間になったように入り込み、彼らの自然の生活、葛藤、喜怒哀楽を淡々と切り取っていく。なぜ外部からのカメラを持った“侵入者”がこれほど自然に家族の“空気”の中に溶け込めるのか。いくらかでも、似たような状況でカメラを回したことのある者なら、その映像に驚くはずだ。中でもルベルの家族が夜、ルベルの通学について口論する場面は圧巻である。なぜ撮影するサーランギ監督がその場にいることが許されているのか、なぜ家族は彼が構えるカメラの前であれほど自然の姿を見せるのか、どのくらいの期間をかけ、どのようにしてあのシーンを撮影できるほどの信頼関係を作れるのか。それはある意味、ドキュメンタリストにとって“企業秘密”なのだろう。Q&Aで私がその質問をぶつけたら、サーランギ監督は、少し笑いながら、「英語にこういう諺があります。『猿を捕らえるには、猿になることだ』」とだけ答えた。実に含蓄のある言葉だ。たしかに「こうすればいい」という定石の答えはないのかもしれない。撮り手の性格、人間性、それまでの人生体験も個人によって全く違うのだから、その手法、対象へのアプローチの仕方も当然、違う。ある人にあてはまることでも、他の人にはまったく当てはまらないだろう。でも、その言葉は、とても重要なヒントを含んでいる。つまり、「猿を撮るには、『猿よりも優れている人間』という意識から、つまり劣ったものを見下す視点からは猿の本当の姿は撮れない。そういう上下、優越の関係ではない、猿と同じ視点、意識から見なければ見えてこない」ということなのだろう。こう書くと、「監督は自分は“人間”、スラムやチョールで暮らす貧しい住民たちを、その人間より劣った“猿”とみなし見下しているのか」という声も出てくるだろうが、サーランギ監督の作品とその人柄に触れたことのある者なら、むしろその対極にある人であることは説明する必要もないだろう。
4年前も私は『ビラル』に感動して、監督に同じような質問をしたことがある。その時のことを当時のコラムに私はこう書いている。
この映画を観て私がまず感嘆したのは、カメラワークである。まさにビラル少年の目線のカメラの位置から、家の中の生活の様子や周辺の状況を見せていく。一方、狭苦しい家の中で子どもたちと両親をアップで映し出す。「撮影者はいったいどの位置から撮っているのか」という好奇心に駆られてしまう。しかも両親も家族もほとんどカメラを意識せずに動き回る。「目が見えない両親は、カメラが接近してもほとんど気づかず、意識しなかったんです」という監督の説明はわかるが、好奇心旺盛なビラルはそうはいくまい。しかしこの少年はカメラ撮影などまったく気にもかけないように自由奔放に動く。監督は、私のインタビューの中で、その疑問に「病院で初めて出会ったときから、撮影を始める3歳になるまで、何度も家に通い続け、ビラルと大の仲良しになっていたから」と答えた。つまり撮影者である監督の存在が、ビラルにとってもう日常の風景になっていたのだ。
『チョール 国境の沈む島』が持つ、もう1つの魅力は映像の美しさと、その映像の並べ方つまり構成力だ。たとえば嵐のシーンでも、暗雲に覆われた荒涼とした大地、暗闇を引き裂く稲妻の光と音、嵐に激しく揺れる木の葉、水面を激しくたたく激しい雨、ゆっくりと崩れ落ちる川辺の大地……それらの映像を畳み掛けることで“嵐”の恐怖、自然の巨大な力を観る者の意識に刷り込んでいく。だからこそ、その過酷な自然の中で、しかも“国境”という不条理な状況の中で懸命に生きようとするルベルの家族のような人間たちの、生き続けるための営みの困難と悲惨さ、そしてその中で必死に生きる姿の愛おしさが、切なく私たちの胸に迫ってくる。そしてこんな過酷な環境の中で人間はなぜこうまでして生きようとするのか、生きるということはどういうことなのかを、私たちに問いかけてくる。サーランギ監督自身は、カタログの「監督のことば」の中で「映画をつくるということは、他者の人生を覗き見ることだ。しかし撮影する側も、映画をつくるという行為から何らかの影響を受けると私は信じている」と語っている。
『チョール 国境の沈む島』予告編
『みんな聞いてるか!』
Are You Listening!
バングラデシュ/2012/ベンガル語/カラー/89分
監督:カマル・アフマド・サイモン Kamar Ahmad Simon

そのことをもっと具体的に語ってくれたのが、映画『みんな聞いてるか!』のカマル・アフマド・サイモン監督だった。この映画の現場も『チョール』の現場に近いバングラデュッシュの大河の沿岸の村。洪水で住処を追われた住民が、自分たちの土地を守るために自ら堤防を造るまでの生活を、ある若い夫婦と独り息子ラフルの家族を中心に据えて描いている。
巨大なサイクロンによってバングラディッシュの広大な地域が大洪水に直面し、首都ダッカで快適な生活を送っていたサイモン監督は、その被害の実態をドキュメンタリーとして記録すべく計画をたてる。当時のコペンハーゲンで開かれていた温暖化防止のための国際会議の議論と現場の実態を組み合わせたドキュメンタリーにするはずだったが、現場で住民たちの中で住み込み、20ヵ月、撮影を進めるなかで、過酷な自然環境と貧困の中で、堤防を造る夢を抱き、たくましく生きる住民たちの姿に引き込まれていく。それは自分を見つめなおすことでもあった。サイモン監督は上映後のトークの中でこう語った。
「住民たちは、いつそれが実現するともわからない堤防完成を夢みていました。私はそれに引き込まれました。私はそれを記録しようと思いました。しかしそれはいつになるのかわからなかった。もしそれが5年後だったら続けられたかわからない。幸い、それは20ヵ月で実現しました。私は彼らの堤防完成の夢を追い撮影すると共に、自分の人生や生活について考えるようになりました。つまり人間が生きることの意味とは何だろうと考え続けていたのです」
この映画のクライマックスは、大河の沿岸の何千、何万という住民たちが力を合わせ人海作戦で、ついに堤防を築き上げていく感動的なシーンだが、映画はそこで終わらない。その後、また嵐がやってきて、ラフル少年の家族の生きるための闘いが続いていく。そしてその最中に映画は唐突に終わる。観る者は、途中で置き去りにされたような落ち着かない気持にさせられ、いったいこの映画の結論は何だったのかと考え込んでしまう。
上映後の質疑応答で、私がそのことを問うと、サイモン監督は「それは円を描くようなものです」と答えた。「この映画は、ある終着点に向かって作った映画ではありません。映画を撮影しながら、これは人間が生きる“円”なのだと気づいたのです。つまり『生活し、子を生み育て、そして夢を見る』というサイクルで、人はそのサイクルを繰り返しているんだと気づいたのです。この映画制作の出発点はサイクロンでした。そして現地の住民たちが堤防を作る夢を追う、そしてまた嵐がやってくる。その時、私は彼らの生活を一巡したと感じました。その時、この映画はもう終わっていいのだと思ったのです」
『みんな聞いてるか!』予告編
『チョール 国境の沈む島』と『みんな聞いてるか!』という2つの作品が類似しているのは、撮影現場や撮影対象だけではなかった。映画で描く家族の姿から、2人の監督たち自身が、そして観る私たちもが、“生きる”とはどういうことかと問われる映画だということだ。だからこそ、インド、バングラディッシュという遠い世界の、まったく違った文化や生活スタイルを持った人間が描き出されたこれらの映画が、私たちの心を動かすのだろう。
2つの映画には決定的な違いもある。それは住民たちの過酷な生活の背景・原因を単に自然の過酷さにだけ求めるのかどうかという点だ。サイモン監督の『みんな聞いてるか!』には、それがほとんど見えてこないが、サーランギ監督の『チョール 国境の沈む島』では、住民たちの過酷な生活を強いているのは、単に自然の猛威だけではなく、自国の利益のためにガンジス川の上流にダムを建設し、その流れを人工的に変えてしまったインド国家にも責任があることを、ダムの映像と、ダムのために河の流れを変えてしまったことを語る監督自らのナレーションで短く伝えている。上映後に監督はこう語った。
「大地は動かない。ただ河の流れが変わっただけなのです。ダム建設によって自国に有利なように流れを変えることで、そこにナショナリズム、国と国の軋轢が生まれ、それに住民が翻弄されているのです」
もしこの作品にサーランギ監督のこの主張が、映像としてもっと具体的に展開されていたならば、この映画はもっと深い映画になっていただろうし、受賞作品の1つになっていたかもしれない。

→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。


