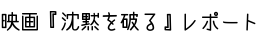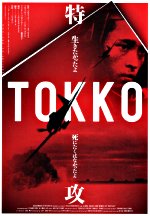映画『沈黙を破る』ゲスト・トーク第8回
佐藤忠男さん(映画評論家)
2009年5月24日(日) @ポレポレ東中野
本日のゲストは、映画評論家で、日本映画学校の校長先生でもある佐藤忠男さん。
佐藤さんは、『沈黙を破る』のパンフレットに、「世界の心の連帯を支える映画」と題して評を寄せてくださっています。土井は、「すばらしい文章を書いてくださった。この映画で僕が言いたかったことをズバリ、理解してくださっている」と、佐藤さんの原稿を読んで感動していました。

佐藤さんの著書『映画の真実─スクリーンは何を映してきたか』(中公新書)の「ドキュメンタリーとデモクラシー」の章は土井のおススメです。
Qは、黒澤明の『羅生門』について書かれた「『羅生門』再考─自尊心と真実─」の部分が印象に残っています。これを読みながら、「沈黙を破る」のメンバーのインタビューを精神科医の野田正彰先生のところへ持って行った時のことを思い出しました。野田先生は、開口一番、「どれだけ、彼らはほんとのことを言ってるのかなぁ」とおっしゃったのでした。この問いかけには「……」でした。これまで、旧日本軍兵士やアジア地域の日本軍元慰安婦をはじめ、多種多様な事柄によってトラウマティックなものを抱えた加害者も被害者も、たくさんインタビューをして来られた野田先生からの直球でした。「全てホントではないかもしれませんが、かなりのリアリティはあると思います。嘘はそんなにないんじゃないかと……」土井はそんな風に答えていました。
佐藤忠男さんの「『羅生門』再考─自尊心と真実─」の章を読み、「証言」とか、最近流行りの「ナラティブ」における落とし穴が明確に浮き出てきました。
そもそも、人間は自分を客観的に記述できるものだろうかという疑問からこの物語(インド映画『モノローグ』)は出発しているのだという。人間には、まず経験がある。これを人間は記憶するが、どの経験を記憶し、どの経験を忘れるかで認識は違ってくるし、また、記憶していることのうちどれを重要だと考えるかでも違ってくる。さらに記憶の修正ということが生じる。……人間は自分自身についての物語の創作者である。
(『映画の真実─スクリーンは何を映してきたか』)
野田先生が「どれだけほんとのことを言ってるのかなぁ」といった意味は、こういうことだったんだなぁ、と理解できました。証言というのは、やはりそういうものが付きまとわざるを得ない。佐藤忠男さんは、黒澤明の『羅生門』について、「想像力や情念による人間の自己美化と自己正当化、その素晴らしさと空しさをこそ描いたものだったといえるのではなかろうか」と書かれています。
人間は、エゴイストで嘘つきだから信用できないというのではなく、もともと各自固有の想像力で認識しているのだから、それが食い違うのは当然であり、にもかかわらず人と人とが心を通い合わせるためには、人びとが共有できるなにかが必要だ、ということである。
(『映画の真実─スクリーンは何を映してきたか』)
この続きは、ぜひ、佐藤さんのご著書でお読みください。素晴らしい本です。
『沈黙を破る』を観て
佐藤:『沈黙を破る』、大変興味深く観せていただきました。以前から、イスラエルでは兵役拒否の動きがあったのは知っていました。それに関心があったんです。結局の所、戦争反対の鍵を握っているのは兵役拒否なんだろうと思っています。最近は、自分の国の戦争について批判的な映画がわりと出ています。それが「常識」になっている。自分の所が絶対正しいなんてのは、時代遅れになっているんです。
ただ、なんだかんだ言っても、国のために死ぬのは美しい、というのはまだ残っていますが。日本でも特攻隊ものはよく出てきますね。ベトナム戦争批判で有名になった『プラトーン』も、米軍の残虐行為は描いています。でも、最後はそのことを自己批判する兵士も、ベトナム人に何をしても構わない兵士も、一緒に全滅するまで戦うという心意気を示すんです。なにがなんでも戦争はやるんだ、といった決め手がある。そこがあるからアメリカ社会で受け容れられる。その共通点さえあればいい、みたいになっちゃうんです。だからこそ、兵役拒否が鍵だと感じるんです。戦場に行かない、弾は撃たない、という兵士が出てこないと戦争はなくならないんだなって。
イスラエル映画って、パレスチナ人に同情的な作品が結構あります。「自分達も、問題をよくわかっているんだ」というところまでは描かれています。でも、そういう人は少数派なんでしょうね。映画人ってのは国際的な感覚を持った人が多く、「自分達が絶対正しい」なんてのを時代遅れとしているんです。だから、『沈黙を破る』も一番肝心なことが描かれていますから、イスラエル・パレスチナを超えて世界で観られていく映画になると思います。
戦時中の体験
佐藤:私の体験を含めて日本のことを話します。日中戦争が始まったのが、小学校1年か2年のときでした。母が、近所の噂を聞いてきて恐る恐る話していたのを覚えています。うちでコソコソ、「近所に中国から帰ってきた若い兵士がいて、中国で兵隊たちがゴロツキと変わらないことをしていると言ってた」と。そういう話をしていると憲兵に捕まったとか言われます。捕まった人も居るかもしれないが、でも根こそぎなんて捕まらなかった。当時の日本人が、中国で起こっていたことを全く知らなかったなんてことはないんです。それくらいの噂話はいっぱいあった。しかし、その程度のものは愛国的な言葉が氾濫している中では「ノイズ」となるんです。そういうような話も聞いたことは聞いたが……それはそれで……と片付けられた。
もっと鮮明に覚えているのは、小学校の講演会で帰還将校が中国人捕虜の首を切るのは「大根を切るようなものだ」と笑って言い、僕たちはどうしたらよいかわからず校長先生を見ると、校長先生が笑っていたので自分達も笑ったんです。その程度のことはいくら隠そうとしても戦場からもれてくる。ただ、それもノイズに過ぎなかった。戦後になっていろんなことがわかってきました。びっくりはするけれど、そういえばそういうことも聞いていたな、とも思うんです。まともに話す機会が戦時中になかった。それを問題だという人もあまりいなかった。圧倒的に「正義の戦争」と言われていた。それが「戦争」なんだろうと片付ける。だんだん慣れてしまう。そういう循環に飲み込まれていく。
小学校の頃、希望的な将来として、満蒙開拓団と少年飛行兵の二つの選択肢を学校の先生達は提示しました。先生が言うからには良いことに違いないと思っていました。満州も、全くの荒野だと思っていました。あの当時の感覚では、中国へ行って日本人が耕す方がよいことだと考えていました。イスラエル人がパレスチナ人の土地を奪うのをへっちゃらと思っているのと似ているだろうと思います。彼らが耕すより自分達が耕す方が価値があるという感覚です。一種の人種差別です。アジア人は劣等であると信じていた。特に中国人は劣等であると。これは私が子どもの頃には牢固(ろうこ)とした常識でした。土地を奪うことも「土地の有効活用」なんて思う。そういう感覚について、今でもうまく語られていないのではないでしょうか。満映(満洲映画協会)の幹部の話を聞いていて、戦争責任を感じませんか、という話になった時、「満州は、無主の(主人のいない)土地だったからいいんだ」と言いましたね。彼らと「沈黙を破る」は重なってきます。だから、「沈黙を破る」のメンバーらのような動きは微々たるものだとは思うのですが画期的で大切だと感じます。
日本では、「沈黙を破る」のような人々が出てきても、その声を聞かない濃密な空気が確かにあります。
映画の中の戦争と「美しい死」の物語
佐藤:日本の戦争責任を自覚的に描いた作品ですか……。全体の中ではいくつかあります。『戦争と平和』『嵐の中の母』が挙げられるでしょうか。でも、要するに、日本の「特攻隊もの」などで描かれる「潔く死ぬことが尊い」というのは変わらないです。
あまり知られていませんが、特攻隊として出撃したのだけれど機体の故障やらで帰ってきた人は意外といるんです。でも、日本映画では、帰って来たことを「恥を知れ」と上官から侮辱されて意地でも死ぬ、というのがパターンです。
その中で、日系アメリカ人の女性監督が作った『Tokko─特攻』(監督:リサ・モリモト、2007年アメリカ)という映画があって、日本人がつくったものと微妙に違います。この作品を見てびっくりしました。彼女の叔父が特攻隊員だったけれど事情があって帰ってきた人でした。その叔父はそれについて語りたがらなかったのですが、彼女は同じような証人を探していきます。通信士と操縦士だった二人を探し当てた。彼らは二人で相談して「帰ろっか」ということになり帰ってきたという。映画の中で「帰ってきてよかった、あはは」としゃべっている。私は今まで、そのような映画は見たことがなかったんです。帰ってきた特攻隊員が「あはは」と笑ってしゃべっているシーン。日系アメリカ人の監督だと「これこそがノーマルだ」とキャッチできた。そういうインタビューが取れる。日本の映画人が作ると、その時彼が「あはは」と笑ったことがキャッチできない。特攻隊ものの『雲ながるる果てに』ではエピソードが少し出てきますが、本格的に扱った次の作品では、やっぱり悔しさをなくすために再び出て行く話になっているんですね。日本の社会の暗黙の了解や常識を外せるから、彼女はそういうシーンが撮れたんです。
『Tokko─特攻』予告編
常識への批判的視点
土井:映画『靖国 Yasukuni』(監督:李纓/リ・イン、2007年日中合作)もそうですね。僕は、あの上映自粛の際に反対の意見を出すことにかかわった一人なのですが、あれは日本人にはできなかった作品だと感じました。今、中国で『南京・南京』(監督:陸川/ルー・チュアン、2009年中国)が話題になっています。日本人が人として描かれていると言って中国では批判されているそうですが、それでも日本で上映するのは難しいでしょう。なぜ、日本人には、「あはは、と笑う」ことが描けないのですか?
佐藤:そういう人がいるにも拘らず、キャッチできないのです。監督が、日本社会を正確に反映しているからです。『私は貝になりたい』という映画で、「(捕虜を)殺さなければ、自分が殺された」と証言します。日本社会ではこれを当然のこととして、こういったシーンを繰り返し映画に出しています。日本人の常識にはなっていますが、そんなことはないんです。捕虜を殺せないダメな兵隊でも殺されたりはしないんです。誇張された言い方です。殴られるくらいのことはあっても、勝手に上官が兵隊を殺すなんて普通の軍隊生活ではありえないことです。でも、そうじゃないことが広く信じられているのが日本社会です。そういう言葉を受け容れ、信じている。それを出せばみんなが納得する。納得という形で、みんなで責任を取ろうって話になる。これってきれいなんです。でも、これは個々が責任を取らないことの象徴です。そうして、一人ひとりに責任があるなんて思わなくてもいいんだ、という濃密な空気を生み出しているのです。
やっぱり、日本社会の暗黙の合意の方が、個人の良心やなによりも重大というのが、我々の社会の常識となっています。同じ日本人でも、日系アメリカ人だと、そこの枠が外れて「あはは」がキャッチできるんでしょう。
自分の国を批判する人をどれだけ受け容れられるかが、文明の発達だと思っています。
30年前に『英雄モラント』という映画を観ました。これはオーストラリア映画が注目された最初の作品です。第二次大戦にイギリス軍の手下として参戦していくオーストラリア軍。誰がゲリラか、農民かわからず手当たり次第に殺していく。それが戦争犯罪とされ、戦犯法廷で争われる。イギリス軍は、そんなモラルのないことをするのはオーストラリア軍だけだ、という。オーストラリア軍はイギリス軍の名誉のために闘ってきたという。イギリス軍は、俺達がやらせたんじゃない、という。
この作品の監督が、「自国の軍隊を批判できるようになるのが民主主義の階段」と言っていました。そういう民主主義の計り方ってあるんだな、とその時に思いました。批判することをみんなが受け容れる社会。日本も少しはできているようだけど、でも、「捕虜を殺さなきゃ自分が殺された」のセリフを疑問も持たず受け容れていては、まだまだだと思う。みんなが言うことに納得しない人間が出てこなければならないでしょう。
今、世界は民族性とか宗教といったものより、別の共通の物語の中にいる気がします。世界共通で「私は殺さない」という権利が当然になることが大切で、その空気が盛り上がってきて欲しい。それこそが普遍的価値観として……。
この夏も、若者が「美しく死ぬ」戦争映画が公開されるようです。宣伝が始まっています。
佐藤さんから、あの時代を生きてきたからこその肌感覚を、たくさんお話しいただきました。特に、戦中の日本の濃密な空気についてのお話は背筋がぞくぞくする感じでした。でも、案外と今もそのような雰囲気にあるかも。「ノイズ」としてしか重要な声を聞けていない日本の社会なのではないかと感じます。
『沈黙を破る』で、ユダヤのことわざ「人の失敗から学べ。全ての失敗を経験している時間はないのだから」をユダが提示します。そうなのですよね。
佐藤さん、本当にありがとうございました。
(文責「土井敏邦 パレスチナ記録の会」Q)
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。