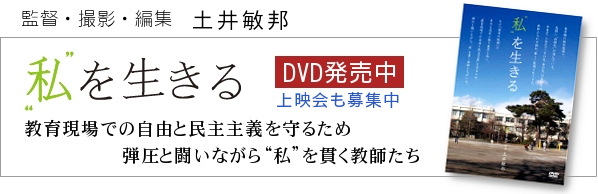土井敏邦・インタビュー
「“伝え手”として生きる」(1)
(2012年10月14日 公開)
これから3回にわたって、月刊「マスコミ市民」(2012年7月号)に掲載された私へのインタビュー記事「シリーズ〈異端〉のジャーナリストに聞く(8) 構造的暴力に対するアプローチ「パレスチナは人生の学校」を掲載する。
「なぜジャーナリストの道を進むことになったのか」「なぜ“パレスチナ”だったのか」「何を伝えようとするのか」「現場で何を学んできたのか」……。これまで公にしてこなかった自分史を、聞き手であるジャーナリストの大先輩、大治浩之輔氏に語ったものである。

大治 浩之輔 氏
おおはる・こうのすけ。1935年生まれ。東京大学法学部卒。1962年NHK入局。東京報道局社会部記者。司法記者クラブ・環境庁クラブ・遊軍を通じて、政治腐敗を追う事件、公害・環境問題を柱に取材活動。イタイイタイ病、新潟水俣病、四日市大気汚染、熊本水俣病、四大公害裁判などをチーム取材。とりわけ水俣病事件については、1972年の第一次水俣病裁判の結審取材に初めて現地入りして以来、社会部を去るまで、継続して追い続けた。
代表的なドキュメンタリー番組に、『ドキュメンタリー 埋もれた報告』(水俣病被害に対する行政責任の追及/1976年12月)。月刊『マスコミ市民』編集人。
夢破れて放浪の旅へ
【大治】 土井さんはご著書以外にも、ビデオジャーナリストとして数々のドキュメンタリー作品をつくられています。ジャーナリズムの全機能を一人で引き受けて活躍されているオールラウンドの方に、このシリーズに登場していただきました。
そもそもジャーナリズムは、不合理に異を立てるところからスタートしていると思います。つまり「異端」のジャーナリストこそ正統なジャーナリストだというのが、私たちの考えです。
私は、これまでパレスチナに関する土井さんのドキュメンタリーを見てきて、現場に徹した一貫した姿勢に感銘を受けてきました。土井さんがジャーナリストとしてスタートしたきっかけはどこにあるのですか。
【土井】 私は小さい頃から医者になることを目指していたのですが、医学部の受験に3回挫折しました。それで周りから「とにかく大学生になれ」と言われて、6月入試を受けて広島大学に入りました。でもそこで何をやっていいのか分からず、ほとんど講義には出ず、3年になっても20単位しかありませんでした。毎日悶々と無為に過ごし、夜は酒を飲んで荒れた生活をしていました。このままでは自分はだめになると思い、世界に出ようと決意したのです。岩国基地の米兵と結婚をした日本人女性について基地に出入りし英会話に慣れ、フランス語学科の友人フランス語会話を習い、牧場の仕事や全国縦断ヒッチハイクの練習をして、孤独に耐える訓練をしたあと放浪の旅に出ました。
小学生の時からアルベルト・シュヴァイツァーに憧れて、その墓の前に立てば、将来の道が見えてくると思い、ガボン(当時の仏領赤道アフリカ)のランパレネにたどりつきました。その後サハラ砂漠を縦断したとき、イスラエルのキブツ(イスラエルの集産主義的共同体)で5年暮らした日本人青年と出会い、彼からイスラエルがいかに素晴しい国かを1ヵ月間毎夜、聞かされました。私はイスラエルの話を聞き「行きたい」という衝動に駆られ、パリまでヒッチハイクし、そこからイスラエルへ飛びました。1978年1月のことです。
当時の私にとって、キブツはパラダイスでした。世界放浪中は、毎日どこで寝て何を食べるかをずっと心配ばかりしていたのですが、キブツは寝食の不自由はなく、緑に囲まれた環境は素晴らしく、理想的な社会主義が実現されている「天国」のように見えたのです。私は早朝から昼まで搾乳の仕事をしました。職場のイスラエル人から、「君は次に生まれるならどこがいいか」と聞かれたとき、何の躊躇もなく、「ユダヤ人としてイスラエルに生まれたい」と答えていました。
ここでの生活が終わる1カ月くらい前に、オランダ人のボランティア仲間に「一緒に旅をしよう」と誘われ、私は何も知らないガザへ連れて行かれました。訪ねた難民キャンプはキブツとは別世界です。ゴミだらけで臭くて、人はごったがえしています。そのキャンプで私は住民の若者たちに囲まれました。彼らにどこから来たと訊かれ、「日本人だが、イスラエルのキブツにいる」と答えました。すると彼らは「君はキブツが誰の土地か知っているのか」「君のいるキブツは、他の民族を犠牲にして生まれた世界なのだ」と言われました。パレスチナ問題などまったく無知だった私は、その言葉に大きな衝撃を受けました。私は1953年生まれで、いわゆる“ベトナム戦争世代”ですが、佐賀の田舎育ちで医学部受験一筋でしたから、社会問題や国際問題に目を向けることがほとんどありませんでした。そういう私が初めて国際問題であるパレスチナ問題と出会ったのです。それまでノンポリで、まっさらな状態だったが故に、その衝撃は、その後の私の人生を変えてしまうほど大きかったんだと思います。
その直後、今度はヨルダン川西岸の難民キャンプを、独りで訪ねました。そこでも忘れられない記憶があります。難民キャンプで皆に囲まれ「何をしに来た?」と訊かれ、私は「パレスチナ人のことを知りたくてやって来た」と伝えました。すると、サウジアラビアで教師をし里帰りをしていた青年が、「それならうちに来い」と誘ってくれました。その家では、難民の家族なのにすごいご馳走が出てきて、満腹になったらタバコも出されました。横になりたいと思ったら枕を用意され、日本の田舎のような、痒いところに手が届くもてなしでした。そのご馳走ともてなしに、私は「何だ、難民だといっても、全然貧しくないではないか」と思ったのですが、そのあとトイレに行こうとして台所の前を通ったら、10人くらいの家族が、私が食べ残した料理で食事をとっていました。あれは衝撃でした。それまでイスラエル人社会の中で「アラブ人は危ないテロリストだ」という「アラブ人観」「パレスチナ人観」を植え付けられていた私が、初めてパレスチナ人の“人間の顔”に出会ったのです。「これから大学でパレスチナ問題を勉強しよう」と決断したのはその時です。
もう一つのきっかけは『戦場の村』
【土井】 私は1年半の世界放浪の旅を終え、国際関係論とりわけパレスチナ問題を勉強したいと思って大学に復学したのですが、大学にはパレスチナ問題を教えてくれる先生はいませんでした。それでイスラエルの週刊新聞やクウェートで発行していた「パレスタイン・ジャーナル」という研究誌など資料を海外から取り寄せました。また当時、パレスチナ問題の著書を出していたジャーナリストの広河隆一さんの本も読んで勉強しました。
当時、広島大学には、社会学者で、ベトナム戦争における人権侵害の実態を体系的に研究していた芝田進午教授がいました。芝田さんのその「基本的人権侵害の体系」を、私が衝撃を受けたパレスチナの占領地の実態に応用してみようと考えました。その結果が、「パレスチナ人の人権侵害に関する一考察」という卒業論文です。それは「暴行を受けたり、殺される」と言った目に見える物理的な暴力ではなく、真綿で首を絞めるように、人間が人間らしく生活していくための基盤、人間としての尊厳を破壊していく、いわゆる“構造的な暴力”を描くことでした。
【大治】 その姿勢は、以後一貫としていますね。
【土井】 そうですね。私の原点はパレスチナの難民キャンプでの人びととの出会いであり、芝田進午さんの影響を受けてかたちづくった“構造的な暴力”の体系です。それ以後のパレスチナに関する20数年間の私のジャーナリストとしての仕事は、“現場”での取材を通して“肉付け”し、“深化”させていく作業だったといえるかもしれません。だから僕は、さまざまな「事件」を追って国内外を飛び回るようなジャーナリストではなく、一つのことにこだわり、追い続けるタイプのジャーナリストと言えるかもしれません。そういう意味で、とても不器用だと思います。
私がジャーナリストになるもう一つのきっかけは、学生時代に読んだ本多勝一さんの『戦場の村』というルポルタージュです。これは、「戦争と民衆」という朝日新聞の連載を一冊の本にしたものですが、この本を学生時代に読んだとき、「ルポルタージュとは、これほど人の心を動かす力があるのか」という、強烈な衝撃を受けました。
今でも覚えていますが、『戦場の村』の一シーンに、南ベトナム軍将校のお兄さんが戦死し、その埋葬のとき、妹が「お兄さん、私を捨てていくの!」と泣き叫ぶシーンがあります。本多さんは乾いた文章で、詳細に淡々とその情景を描写しています。読者はまるで映画でも見ているように、その情景を思い浮かべることができるのです。その文章を読んだとき、ルポルタージュの力に圧倒され、しばらく呆然としました。「一生に一度でいいから、こういうルポルタージュが書きたい。その後の人生はどうなってもいい」と心底思いました。これが、私がジャーナリストを志すきっかけです。
私は放浪の旅から帰ってから専門コースを変更しましたから、卒業までに7年かかりました。すでに浪人生活で3年遅れていましたから、卒業するときは、すでに28歳になっていました。就職しようにも年齢制限でどこも採ってくれません。新聞社の受験にも失敗したので、東京に出て、活字媒体の創作集団のアルバイトをすることになりました。ところが、自分が目指すこととはまったく違い、旅行記やスポーツの記事を書くような仕事ばかりでした。「なんでこんなことをやっているのだろう」と思っていたときに、卒業論文を読んでもらった広河隆一さんから、「まだパレスチナ問題に関心があるのなら、雑誌の記者をやってみないか」と誘われ、彼が編集長だった『フィラスティン・ビラーディ(パレスチナ・わが祖国)』という月刊誌の記者になりました。
【大治】 記者になったのは、卒業してからすぐでしたか?
【土井】 半年後です。仕事に就いた途端、5ページの人物ルポを書くように言われました。新聞や雑誌の「人」の欄などを読んで独学し、土井たか子さんなど著名人にもインタビューをして記事を書き始めました。写真も、プロのカメラマンから「四隅を見ていない」などと酷評されながら、基本的なことを学んでいきました。今振り返れば、当時、雑誌編集部に出入りしていたプロのジャーナリストやカメラマンたちに批評してもらいながら勉強できた、ずいぶん贅沢な修行時代だったと思います。新聞やテレビ局の中東特派員だったジャーナリストたちや、中東の研究者たちとの出会いもありました。2年間足らずでしたが、勉強になりました。
私にとって、雑誌編集記者の仕事は占領地のルポルタージュを書きたいがための修行でした。当時、日本の特派員はテルアビブに1人いるだけで、占領地に関する記事のほとんどは、イスラエルのテレビや地元紙、外信が主な情報源だったと思います。占領地は、日本のジャーナリストがあまり踏み入れない、いわば空白地帯でした。私はその占領地を舞台に『戦場の村』のようなルポルタージュを書きたい、という願いがありました。本多勝一さんの著書から学んだように、住み込んで現地の人びとの生活と心情を描き、人間の生の姿を描き出す、定点観測をしたかったのです。
『戦場の村』の元となった新聞連載記事「戦争と民衆」が大きな反響を巻き起こした理由の1つは、その構成の巧みさでした。本多さんは、1章から4章まで、サイゴンの市民、山地の人々、デルタの農民など、様々な人々の生活、たとえば何を食べているのか、トイレはどうなっているのか、お祈りはどうするのかなど、淡々と人々の生活の詳細を乾いた文章で描きました。そうすることで、「ベトナム人」という総体ではなく、等身大で固有名詞の個々人の顔が浮かびあがってきます。つまり顔のない「ベトナム人」ではなく、私たちと同じ個々の人間の姿が読者の中に、無意識に刷り込まれていきます。
そして、第5章「戦場の村」になって初めて、「その私たちと同じ人間に、こんな悲惨なことが起こっているんだ」と、戦争被害の実態を克明に描くのです。それは、ベトナム人の個々人の顔が無意識に刷り込まれていた読者に、ものすごく衝撃を与えました。
私は「これだ!」と思ったのです。「パレスチナ人」という、顔の見えない総体ではなく、一人ひとりの等身大の姿、顔や生活を丹念に描き伝し、読者や視聴者に「パレスチナ人も自分たちと同じ人間なのだ」という意識を植え付けていく、つまり“占領”というのは「アリという1人の人間が、生きていけなくなっていくことだ」「そんな個々人の問題の総体が、パレスチナ問題なのだ」というように描いていく手法、それを私は本多勝一さんの『戦場の村』から学びました。
【大治】 今日は、土井さんの定点観測、腰を落として粘り強く現場に徹する取材方法。そのような取材手法をなぜとるようになったかをまず知りたかったのです。
【土井】 私のもう一つの基本は卒業論文の指針です。つまり、殴られた、撃たれたというセンセーショナルな暴力だけに問題があるのではなくて、人間の生活の基盤を破壊されていく“暴力”、真綿で首を絞められ、生きていくことができなくなる環境がつくられること、それが占領であり“構造的な暴力”なのです。そこを描かないとパレスチナの本当の苦しみはわかりませんし、人間の顔は見えてきません。
【大治】 先ほど土井さんは、ご自身を不器用だといいましたが、不器用には恐るべき力がある。「雨垂れ石を穿つ」ではありませんが、コツコツと持続してたいへんな結果を生みます。ジャーナリストの大事な要素の一つは、持続してやり抜く一貫性です。繰り返し現場へ行く、徹底して現地の人たちの中に身を置く、簡単に誰でもできることではありません。
【土井】 私がそうした取材ができたもう一つの理由は、挫折して自分に自信を失ったことです。どう生きていくべきかわからない自分を抱えて現場へ行ったとき、あれほど過酷な状況の中でも人間性、人としての優しさ、豊かさを失わない、すごい人たちがいました。私たちと比べて貧しいかもしれない、モノなど十分ないかもしれないが、どちらが人間として豊かなのか、人間としての生き方、在り方を見せつけられました。人は状況が厳しくなればなるほど醜い部分もたくさん見えてきますが、人間の美しさもピカッと光るんです。それが占領地での人との「出会い」だったのです。
【大治】 その体験は、土井さんの生き方にかかわり、ジャーナリストとしての基本姿勢にも後々取り上げることになるテーマの選択の仕方にもかかわる、という印象をもちます。
【土井】 自分の道を模索してアフリカに行き、「あの地平線まで行けば何か見えるかもしれない」と進んでみたものの、そこには何もありませんでした。そうやって、自分のなかで生き方を必死に模索していたからこそ、“パレスチナ”と出会い、その後の自分の進路を変えてしまうほど衝撃的だったんです。“水俣”と出会ってそう感じる人もいるでしょうし、“沖縄”と出会ってそう感じる人もいるかもしれません。たまたま、私にとっては“パレスチナ”だったのです。
(つづく)
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。