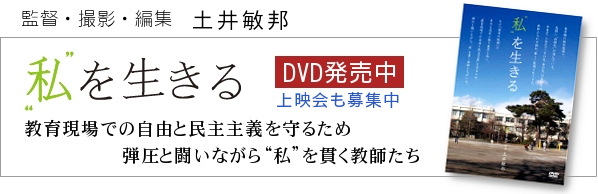土井敏邦・インタビュー
「“伝え手”として生きる」(2)
(2012年10月17日 公開)
難民キャンプに住み込み現場をまわる
【土井】 占領地での長期取材には多額の費用がかかります。その資金作りのために選んだのが、サウジアラビアでの海外駐在員の仕事でした。1984年、私はサウジ東部のアルジュベールという大きな工業都市で、ある小さな日本企業の支店長の仕事に就きました。そこでの1年間は、自分専用の会社の車を持ち、パキスタン人のコックが自分のために日本料理をつくってくれる、それ以前も以後も経験したこともない、恵まれた生活でした。しかし、サウジ人との交流もなく、ほとんど娯楽もない無味乾燥な日々でした。だからルポルタージュを読みあさりました。さらに私にとってルポルタージュのお手本だった『戦場の村』を章ごとに構成を分析し、勉強しました。
会社が半年に一度、休暇として海外に出してくれましたので、私はフィリピンに行きました。会社のスタッフにフィリピンからの出稼ぎ労働者がたくさんいました。彼らは長い間、家族と離れてなぜサウジにやってくるのか、その家族に取材したいと思ったのです。その結果をまとめたルポルタージュ『輸出されるフィリピン人出稼ぎ労働者たち』は、「朝日ジャーナル・ノンフィクション大賞」の入賞作になりました。それは私にとって初めての賞で、ルポルタージュを書くうえで少し自信になりました。
雑誌編集記者時代に、私は韓国を取材し、『韓国の被爆者たち』というルポルタージュを書いています。広島で暮らした大学時代から、私はいつも「ヒロシマ」だけが強調されることに疑問をもっていました。広島で韓国人の被爆者と出会うことで、「一体誰が被害者なのか」という視点をもちます。日本人は「被害者」の顔ばかり強調していいのか、被爆者であると共に植民地主義の犠牲者だった韓国人被爆者こそ、被害者ではないのかと考えたのです。その後、私は韓国の「従軍慰安婦」や南京など、日本の戦争加害の歴史を自分のテーマとするようになります。その一方で“パレスチナ”を追い続けていきました。まったく接点のないように思われた2つのテーマが、初めて重なったのが『沈黙を破る』でした。私は占領者となって人間性を失っていくイスラエル将兵の姿に、中国大陸で人間性を失っていく旧日本軍将兵の姿を重ね合わせたのです。
駐在員として1年間働き、200万円くらい貯まりました。会社を辞めて2か月の準備期間を経て、1985年の5月から占領地のヨルダン川西岸に入り、ラマラ郊外の難民キャンプに隣接するパレスチナ人の家庭に住み込みました。農地を奪われ農民として生きていけなくなる実例、教育の基盤が奪われていく実例、工業が成り立たなくなる実例など、“構造的な暴力”を一つひとつ現場で取材していきました。
その取材の拠点となったのが、ビルゼイト大学でした。当時から“占領への抵抗の拠点”として世界に広く名前を知られていた大学で、占領地各地から優秀な学生たちが集まっていました。その学生たちと知り合い、彼らの故郷を訪問するかたちで、占領地各地を訪ね歩きました。村へ行けば、数日彼らの家に滞在して農民の生活を描く、ガザの難民キャンプに行けば住民の生活状況を描く、そのように知り合った学生たちを通して1年半、占領地を取材して回りました。
【大治】 大学で知り合った人を頼りに各地に入っていくとは、うまいやり方をやりましたね。
【土井】 そうですね。当時、外国人がパレスチナの片田舎を訪ねてくることはめったになく、それは周囲には自慢になるのでしょう、快く実家に迎え入れてくれるのです。
ビルゼイト大学には外国人対象の夏期講習があり、私はそこでアラビア語の日常会話と社会学の講義を受けました。講義そのものはほとんど身につきませんでしたが、そこで知り合った人たちは、その後の私の取材に大きな支えとなっていきます。例えば、親しくなったユダヤ系アメリカ人に導かれるように、その後、私はアメリカのユダヤ人社会を追うことになります。
アラビア語が読めない私は、地元の英字新聞のニュースを読むと、村と当事者の名前だけを手掛かりに乗り合いタクシーで現場へ向かいます。村に着くと、片言でも英語を理解できる青年を探し出し、当事者の家に案内してもらいます。「日本人でビルゼイト大学に通っている」と自己紹介をすると、相手は「こちら側の人間」だと判断し心を開いてくれます。私の英語を青年がアラビア語で通訳すると、取材相手はアラビア語で状況を語ってくれます。それを録音し、ビルゼイト大学に帰って知り合いに訳してもらいます。その答えに新たな疑問が出てくれば、また現地に戻り、同じように取材する。そうするうち録音テープが膨大な量になってしまいました。すると、知人の英語の先生が大学の講義で「今日の授業は翻訳で、このテープが素材です。これは授業ですから成績に反映されます」と、授業の中で、英訳を手伝ってくれました。そのように多くの人たちに助けられながら、膨大な素材を集めて行きました。
私は「ノンフィクション大賞」の入選以来、「朝日ジャーナル」とのコネクションができ、パレスチナ問題に関心があった故・伊藤正孝副編集長を通じて記事を送り、掲載してもらいました。しかし、外国人ジャーナリストが占領地に滞在していることをイスラエル当局に知られるのはまずいと思い、毎回名前を変えて記事を掲載してもらいました。それでも当局に気付かれてしまったらしく、ある日私の留守中の下宿先にイスラエルの警官が訪ねてきたと家主に知らされました。私はあわてて素材や資料を外国人の友人のアパートに移し、一時、西岸からガザへ避難しました。

そんな危険もありましたが、1年半後、素材と資料を無事日本に持ち帰ることができました。しかし、今度は執筆の場所と生活費に困りました。実家と広島の留学生寮で半年ほどかけて書きあげたのが、私の最初の著書『占領と民衆 ─パレスチナ─』(1988年 晩聲社)です。占領地でのパレスチナ人の産業基盤が破壊、教育の破壊など“構造的な暴力”の実態をルポルタージュとして描きました。
実は、私はパレスチナからまっすぐには帰国しませんでした。パレスチナを考える際にはアメリカのユダヤ人のことを知らなくてはいけないとユダヤ系アメリカ人の友人に教えられ、「なぜアメリカがイスラエルを支援するのか」を取材するため、直前に帰国したその友人を追うようにアメリカへ向かいました。その友人の人脈を頼って、ニューヨークやワシントン、シカゴなどのユダヤ人を訪ね歩きました。その時は形にはなりませんでしたが、将来の『アメリカのユダヤ人』を取材する基盤ができました。

帰国して『占領と民衆』を書き上げた後、就職して普通の生活をしたいと願っていました。ある非営利団体への就職が内定したのを機に、1987年12月、当時親しかった女性が留学していたサンフランシスコ郊外のバークレイ市を訪ねました。しかしその直後、パレスチナでインティファーダ(イスラエルの占領に対する民衆の抵抗運動)が勃発しました。「ニューヨークタイムズ」「ワシントンポスト」などアメリカの主要紙やテレビの3大ネットワークも連日、トップニュースでパレスチナでの出来事を伝えました。パレスチナを長く取材した者として、じっとしていられなくなり、結局、ニューヨーク経由でパレスチナへ飛びました。現地で1ヵ月、さらにアメリカに戻り国内のユダヤ人やパレスチナ人社会の反応を1ヵ月ほど取材しました。
そのため、内定していた就職先に約束の時期まで行くことができず、就職を断られてしまいました。それなら仕方ないと、やりかけた「アメリカのユダヤ人とパレスチナ人」の取材を完成るために再び渡米し、通算9ヶ月間ほど、バークレイを取材基地にして、アメリカ各地でユダヤ人とパレスチナ人を訪ね歩きました。その結果、1991年に完成したのが、『アメリカのユダヤ人』(岩波新書)と『アメリカのパレスチナ人』(すずさわ書店)という2冊です。

ですから、最初からまっしぐらにジャーナリストとして生きようという気持ちではなかったのです。いま現在やりたいことに夢中になっている間に潰しが利かなくなって、「この道で生きるしかない」と腹をくくらざるをえなくなったのです。もう30代後半でした。
穴場を探して定点観測すること
【土井】 1990年夏にアメリカに取材へ行ったとき、湾岸危機が起きました。クエート侵攻で、アメリカのユダヤ人の反応、パレスチナ人の反応を取材し「朝日ジャーナル」に記事を送りました。帰国して数カ月後の冬休み、今度は「ジャーナル」の臨時特派員としてイスラエルに行きました。ちょうど私が取材を終え出国しようと夜、イラクからイスラエルへスカッドミサイルが飛んできました。湾岸戦争です。予定を変更してイスラエルから見た湾岸戦争を記事にしました。
【大治】 不思議と、行くときに起こるものですね。
【土井】 そうなのです。次々と変化するパレスチナや中東の状況が、私を「ジャーナリスト」に押し留めたというのが実情です。
【大治】 取材のなかで決定的な“出会い”があり、「この道一筋だ」と走ってきたのかと思っていましたが、そんな単純なものではなかった。
【土井】 取材のたびに多くの人と出会い、自分の生き方も問われます。「なぜあなたは20数年もパレスチナに関わっているのか」と聞かれますが、最初から意図したのではなく、現地の人々に魅せられて離れらなくなったのです。同時に、雑誌の記事や著書で周囲から「パレスチナの土井」という目で見られるようになり、それにきちんと応えていかなくてはという思いも幾分ありました。
【大治】 これだけ長い間パレスチナに通った人は、組織メディアにはいませんね。
【土井】 そうですね。例外的なケースでは「朝日新聞」の川上泰徳さんくらいでしょうか。今の新聞やテレビは“専門家”を育てようとはしていないと思います。
【大治】 マスコミを、組織ジャーナリズムをどう見ていますか。
【土井】 「フリーランスは組織ジャーナリズムと違って深く取材ができる」と言う人がいます。しかし、私は映像に関していえば、NHKのETV特集に育てられました。ですから身をもって組織ジャーリズムのすごさを知っています。NHKの七沢潔さんがきっかけをつくってくれて、私が撮った映像をETV特集で放映してもらうようになりました。その編集作業を通して、私は映像の基礎を学びました。またNHKの優秀なディレクターたちや編集者たちとも出会い、多くのことを教えてもらいました。
昨年夏、NHKのドキュメンタリー『飯舘村』を観たときは、私は衝撃でしばらく立ち上がれませんでした。私も4月から飯舘村の取材を続けドキュメンタリー映画を制作しようとしていましたが、「こんなドキュメンタリーが放映された後では、もう作れない」と思うくらい、組織ジャーナリズムの力、特にNHKのドキュメンタリー制作者たちの凄さに圧倒されたのです。私は長年、NHKの中で、私がどんなにばんばっても敵わない凄いドキュメンタリーを作ってきた七沢潔さん、大森淳郎さん、鎌倉英也さん、宮本康宏さん、山口智也さんのようなディレクター(ジャーナリスト)たちの仕事を身近で見てきましたので、「組織ジャーナリズムはだめだ」なんてまったく思いません。あの人たちができない、こぼれたテーマや現場を探し出し、私たちにしかできない取材方法で長期に渡って定点観測することが、私のようなフリーランスのドキュメンタリストに残された道なのだろうと思います。
【大治】 組織ジャーナリズムができない、できなかった仕事の話をしましょう。土井さんは、『届かぬ声─パレスチナ・占領と生きる人びと』というパレスチナの作品(4部作)をまとめていますね。イスラエル側の計画的、構造的な暴力がじわじわとパレスチナ側の生活基盤を侵蝕し壊していく、パレスチナの人たちが人間的な条件を剥奪されていく姿を、実によく描いていて、見ているこちらの心に深い怒りがわいてくる。
『届かぬ声』第2部『侵蝕─イスラエル化されるパレスチナ』を観たときに、すごいと思ったのは、時間をかけていることですね。イスラエル側の侵蝕は一度や二度現場に入っただけではすぐわからない。時間の経過とともに追っていくとはじめて、イスラエル側が街を囲い、畑を囲い、水を奪い、家を奪い、コミュニティーを破壊していくのがわかります。すごい圧力と剥奪が、時間のなかで出てきます。土井さんが10年、20年と追ってきたからこそ、それを的確につかまえられた。それが第一。
もう一つは感心したのは、「合わせ鏡」という言葉も使われていますが、取材の姿勢です。丹念な取材が、パレスチナ側と、イスラエル側の双方に深く入り込む、それぞれの内部にある矛盾にまでカメラを向けようとする。たとえば、イスラエル側とパレスチナ側との間で撃ち合いがあったとき、イスラエルの家庭にもパレスチナの家庭にも銃弾が飛び込む。その双方の家庭の双方の母親から、子どもから、そして学校の生徒たちから話を聞き、対立構造の深さに迫る。イスラエル側の取材でも、「侵蝕をどんどんやっていくべきだ」という発言をする人、それを批判する人、というように、常に多層に構造を捉えようとしています。時間をかけて、ひとつのところで穴を掘っていく、構造的に情報が組み立てられていて、取材姿勢に見合った成果が成立しています。これは簡単ではない、ものすごいエネルギーのいることで、舌を巻きます。
【土井】 4部作のなかで、私がいちばん観てほしいと思っているのは第2部『侵蝕』です。私がパレスチナで追い続けてきた“構造的な暴力”の実例を、最も象徴的に表している作品だからです。時間をかけなければ構造は見えてきませんので、特派員のように様々な「事件」を追いかけていたら、こうした作品はできないと思います。フリーランスの強みがあるとすればそこだろうと思います。
【大治】 このドキュメンタリーの中で、もう一つからだが震えるような衝撃を受けたシーンがある。オリーブの木の破壊のシーンです。先祖代々大事に受け継いできたオリーブの木を、侵蝕してきたイスラエルのブルドーザーが根こそぎにして、廃棄していく。現場に駆けつけた持ち主の老農夫が衝撃で気絶する。見ているこちらの心臓にグサリとくる情景です。
【土井】 あれは定点観測のなかで、偶然に撮れたのです。ある農民にインタビューをしているとき電話がかかってきたので、途中で中断して彼についていくとあのシーンになるのです。パレスチナの専門家の臼杵陽さんが私のあの映像をみていて「オリーブの木が泣いている」と表現しました。確かに木が根こそぎにされるとき聞こえる「きゅーっ」という音は、木が悲鳴を上げているように聞こえます。あのときは「この瞬間を逃さずにおくものか」という気持ちがあったのだと思います。あの現場にいたガードマンが民間人ではなくイスラエル兵だったら、私は暴行を受けてテープを没収されるか撃たれていたかもしれません。4部作のなかでも歴史的価値のあるシーンでしたが、偶然は偶然に来るのではなく、それが来るまでじっと待つ時間がなければ、その瞬間は撮れません。
【大治】 まったくその通りです。基本的な取材姿勢が決定的なシーンに遭遇する必然性をもたらします。それは、現場に通い続けるジャーナリストだけがもつチャンスですね。
(つづく)
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。